 虫歯
虫歯

概要
1. 概要
虫歯になったことはありませんか?
20歳以上の日本人の約9割が虫歯になったことがあると言われています。それは、甘いものの食べ過ぎだけでなく、歯磨きや歯のケアが不十分なことも原因とされています。
しかし、遺伝的要因(体質)も虫歯のなりやすさに関わっていると言わ>ています(参考リンク1)。
自分が虫歯になりやすい体質なのかどうか、遺伝子検査を利用して調べてみませんか?
2. 理論的根拠
虫歯は「う蝕(うしょく)」とも呼ばれ、ミュータンス菌などが作り出した酸によって歯が溶かされる病気です。酸によって歯が溶かされることを脱灰と呼び、進行すると歯に痛みが出ます。
この原因遺伝子の一つとして見つかったのが、11番染色体に存在する遺伝子「BCOR (encoding BCL6interacting corepressor)」であり、この遺伝子に属する様々なDNA領域の一つが「rs17145638」です。
このDNA領域は、約2,000人の白人を対象に行われた遺伝的多型を調べた解析で、歯の表面の「う蝕」に関連して多型のあるDNA領域として発見されました(参考リンク2)。
「rs17145638」には、「TT型」、「TC型」、「CC型」の3つの遺伝子型があります。 日本人の遺伝子タイプは、「TT型」98.2%、「TC型」1.8%、「CC型」0.1%となっています。(参考リンク3)
また、「BCOR」は、歯の形成に関わる遺伝子でもあります。DNA領域「rs17145638」が、Cを含む「TC型」や「CC型」のタイプだと、歯の形成が不十分になり、正常な場合に比べると歯がもろく、虫歯になりやすい可能性があるとされています。
特に「CC型」だと、虫歯の進行がより速くなるので、歯に穴が空きやすく、痛みを感じやすくなるとされています(参考リンク4)。
3. 作用機序
歯は表面にエナメル質があり、その内側に象牙質が存在し、さらに内側は歯根と呼ばれる神経などがある領域があります。
虫歯菌(ミュータンス菌など)は、糖質を栄養源にして酸を作り出すことで、歯を溶かし、歯の表面から内側に侵入していきます。
虫歯菌が象牙質に到達すると、多くの場合、歯に痛みを感じるようになります。
遺伝子「BCOR」は、歯の形成に重要な役割を果たしており、歯の形成過程の初期段階において、象牙質の形成と歯根の発達に関わるとされています(参考リンク4、5)。
DNA領域「rs17145638」が、「TC型」や「CC型」となると、歯根を守るための象牙質の形成が不十分となり、「TT型」に比べ歯がもろく、虫歯になりやすくなる傾向があります。
また、歯根の発達も不十分となるため、歯が折れやすくも、抜けやすくもなる可能性があります。
歯は再生ができないため、現在の歯を大切にすることが必要となります。甘いものの摂り過ぎに注意し、歯磨きなどの適切なケアを行うことは重要です。
遺伝子領域rs17145638において日本で各遺伝タイプを持つ人の割合
- TT99.9%
- TC0.0%
- CC0.0%
遺伝子領域rs17145638において世界で各遺伝タイプを持つ人の割合
- TT77.5%
- TC20.9%
- CC1.4%
遺伝子領域rs5922945において日本で各遺伝タイプを持つ人の割合
- CC65.4%
- CT30.8%
- TT3.6%
遺伝子領域rs5922945において世界で各遺伝タイプを持つ人の割合
- CC58.8%
- CT35.7%
- TT5.4%
遺伝子領域rs10048146において日本で各遺伝タイプを持つ人の割合
- AA49.9%
- AG41.4%
- GG8.6%
遺伝子領域rs10048146において世界で各遺伝タイプを持つ人の割合
- AA67.2%
- AG29.5%
- GG3.2%
 検査の理論的根拠
検査の理論的根拠
体表的なDNA領域:虫歯
体表的なDNA領域:虫歯
虫歯 に最も強く影響する遺伝子領域は、rs17145638です。 日本における同型の遺伝子タイプの分布は下記のとおりです。
-
TT
99.9% -
TC
0.0% -
CC
0.0%
他に、虫歯に関わる遺伝子領域はrs5922945があります。 日本における同型の遺伝子タイプの分布は下記のとおりです
-
CC
65.4% -
CT
30.8% -
TT
3.6%
他に、虫歯に関わる遺伝子領域はrs10048146があります。 日本における同型の遺伝子タイプの分布は下記のとおりです
-
AA
49.9% -
AG
41.4% -
GG
8.6%
 今回調査したDNA領域
今回調査したDNA領域
細胞中に存在するDNAマップの模式図
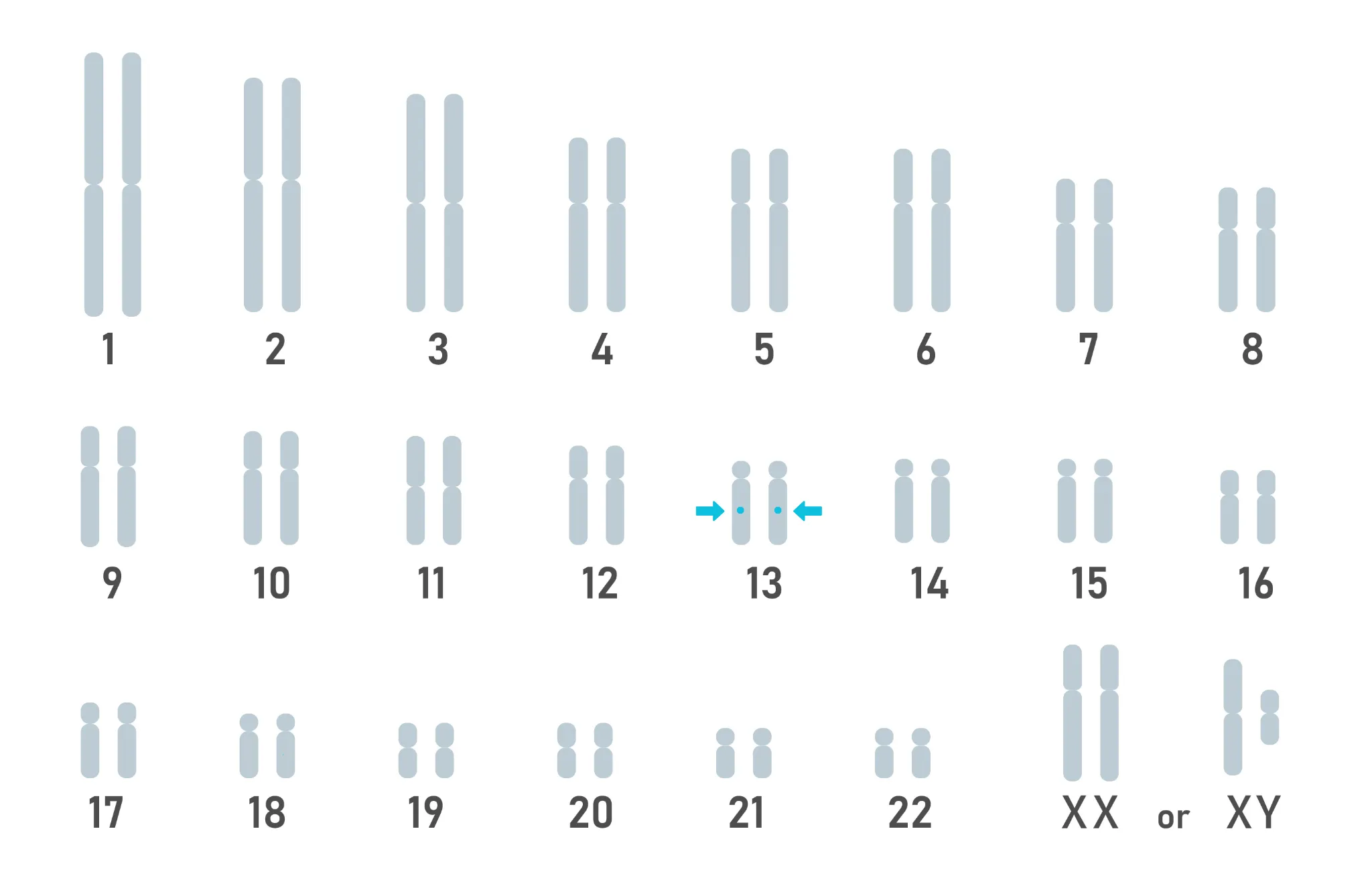
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
 関連遺伝子
関連遺伝子
| 関連遺伝子 | LINC03053 |
|---|---|
| 関連遺伝子 | MIR548I4 |
| 関連遺伝子 | FOXL1 |
 参考文献
参考文献
- 参考リンク1 : 2010 Jul., X Wang, Caries research.
- 参考リンク3 : DNA 領域「rs17145638」の情報 NIH
- 参考リンク6 : 2013 May., Z Zeng, J Dent Res
