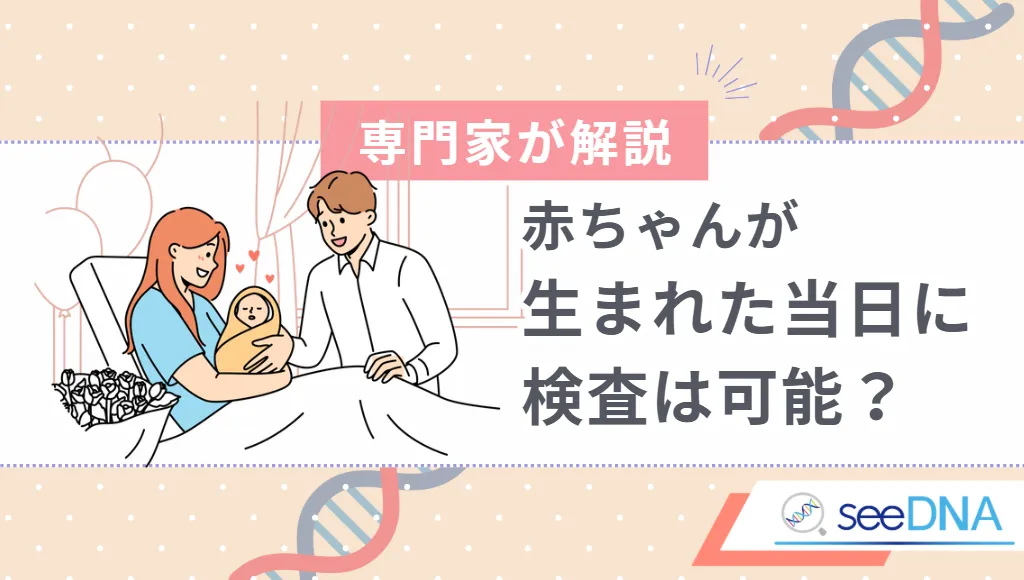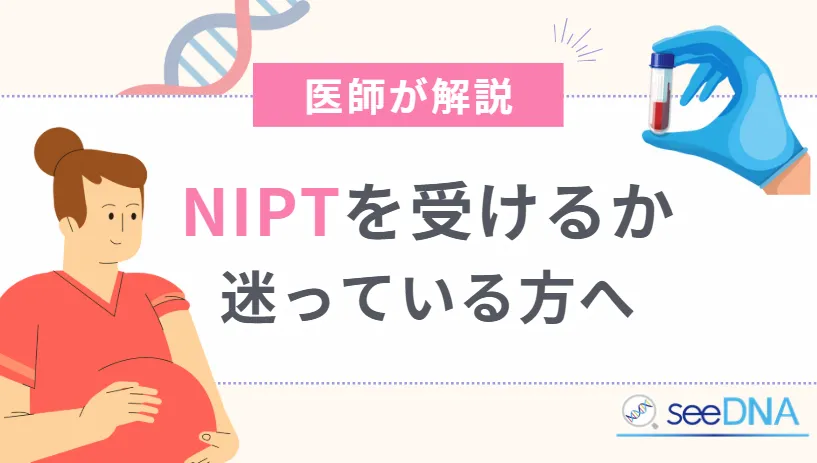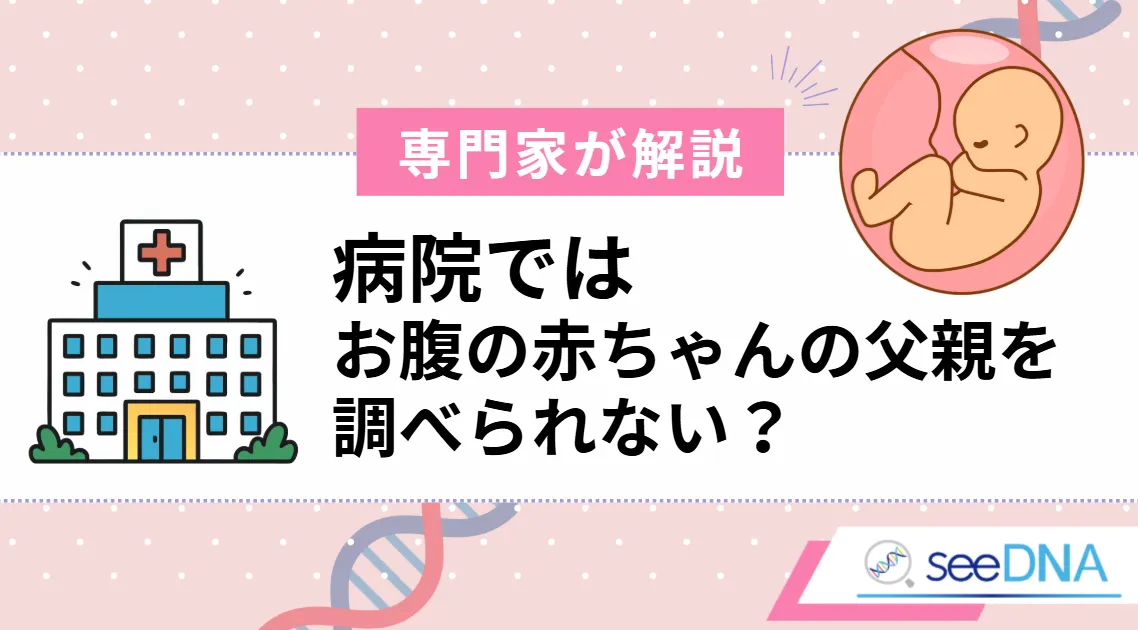【医師が解説】ダウン症に対する、エコー検査、コンバインド検査、新型出生前検査(NIPT)の精度比較
2025.07.08
不安を安心に変えるために――新型出生前検査を知る第一歩

妊娠がわかった喜びと同時に、「赤ちゃんは健康に生まれてくるだろうか」という不安を感じるのは、多くの妊婦さんに共通する自然な気持ちです。特にダウン症などの染色体異常については、現在複数の検査方法が存在し、それぞれ異なる特徴を持っています。しかし、検査ごとに特徴が異なるため、「どれを選べばよいのか分からない」という声も少なくありません。
本記事では、エコー検査・コンバインド検査・新型出生前検査(NIPT)の特徴と精度を比較し、あなたに合った検査選びの一助となる情報をお届けします。
3つの検査の基本的な違い

エコー検査(超音波検査)
エコー検査は、超音波を使って胎児の形態を視覚的に評価する検査です。妊娠11週以降に首の後ろのむくみ(NT:Nuchal Translucency)を測定することで、ダウン症を含む染色体異常のリスクを推定できます。※1
この検査の特徴は、胎児の「形」を直接観察できることです。ダウン症以外にも心臓や脳、腎臓などの先天性異常を発見する重要な役割を果たします。ただし、あくまで形態的な変化を見る検査であり、染色体異常そのものを直接検出するわけではありません。

コンバインド検査
コンバインド検査は、妊娠11〜13週頃に実施する複合的な検査です。エコー検査によるNT測定と、母体血液中の胎児・胎盤由来のホルモン(hCG、PAPP-Aなど)の値を組み合わせ、母体年齢も加味してダウン症を含む染色体異常のリスクを統計的に算出します。※2 この検査では確率として結果が示されるため、スクリーニング検査として有用性が高い一方で、実際にはダウン症ではないのに「リスクが高い」と判定される偽陽性や、逆にダウン症なのに「リスクが低い」と判定される偽陰性の可能性があります。

NIPT(新型出生前診断)
NIPTは、母体血液中に含まれる胎児由来のセルフリーDNA(cfDNA)を解析する最新の検査です。妊娠10週以降から実施可能で、採血のみで行える非侵襲的な検査でありながら、染色体異常をより直接的に評価できるのが最大の特徴です。※3
検査精度の比較
出生前検査を選ぶとき、気になるのが「どれだけ正確に異常を見つけられるか」という点です。ここで大切になるのが、検査の「精度」です。精度にはいくつかの指標がありますが、特に注目したいのが以下の4つです。
- 感度
- :異常が「ある」赤ちゃんを、きちんと見つけられる力です。感度が高いほど、「見逃し」が少なくなります。
- 特異度
- :異常が「ない」赤ちゃんを、正しく異常なしと判断できる力です。特異度が高いほど、「誤って陽性になる」ケースが少なくなります。
- 陽性的中率
- :陽性と出たとき、それが本当に正しい確率のことです。つまり、「陽性=異常がある」と信じてよいかどうかを示します。
- 陰性的中率
- :陰性と出たとき、本当に異常がない確率です。これが高ければ、「陰性=安心していい」と言えます。
このように、単に「陽性・陰性」と結果を受け取るだけでなく、「その結果がどれだけ信頼できるか」を知ることが、検査選びやその後の判断にとってとても重要です。
エコー検査の精度
エコー検査単独でのダウン症検出における感度は約70%前後とされています。※1画像所見による間接的な評価のため、特異度にも限界があります。
コンバインド検査の精度
コンバインド検査の感度は82〜87%、特異度は約95%と報告されています。※2ただし、陽性的中率は母体年齢に大きく影響され、特に若年妊婦では偽陽性率が高くなる傾向があります。
NIPTの精度
NIPTは感度99.3%、特異度99.9%と極めて高い精度を示します。※4ダウン症の陽性的中率は、40歳の妊婦では約90%以上とされています。特に注目すべきは陰性的中率がほぼ100%に近いことで、陰性結果であれば非常に高い安心感を得ることができます。
シチュエーション別・あなたに合った検査の選び方

高精度な結果を求める方にはNIPT
35歳以上の妊婦さんや、できる限り正確にリスクを知りたい方には、NIPTをお勧めします。妊娠10週から検査可能で、ダウン症に対する99%以上の高い検出率を誇ります。※3陰性的中率も非常に高いため、「陰性であればほぼ安心」という心理的な安定を得やすいのが大きなメリットです。
更に、ダウン症候群だけではなく、1回だけの採血でエドワーズ症候群、パトウ症候群、ターナー症候群、クラインフェルター症候群、トリプルX症候群、XYY症候群、全染色体数異常のリスクが一緒に調べられます。

費用を抑えたい方にはコンバインド検査
NIPTの検査項目は多いですが、最安の検査でも79,800円かかるため、費用面を重視し、公的医療機関での検査を希望される方には、コンバインド検査が適しています。
妊娠11〜13週に実施でき、NIPTと同様に早期のリスク評価が可能です。費用が比較的安価で多くの医療機関で実施可能ですが、検査精度はNIPTに劣ることを理解しておく必要があります。

まずは通常の検査から始めたい方にはエコー検査
妊婦健診の範囲内で、まず基本的な情報を得たい方には、エコー検査から始めることをお勧めします。
胎児の成長や形態を確認でき、専門的なエコー検査ではNT測定や臓器の詳細な観察が可能です。ただし、より詳細なリスク評価が必要な場合は、追加検査を検討することになります。
自分に合った検査を選ぶことが、納得の出産につながる

エコー検査、コンバインド検査、NIPTは、それぞれ異なる特徴と精度を持つ検査です。重要なのは、ご自身の状況、価値観、経済的な条件を総合的に考慮して、最も適した検査を選択することです。
どの検査にも限界があり、確定診断が必要になる場面もあることを理解しておきましょう。
また、検査結果に対する心理的な準備も大切です。陽性結果が出た場合の対応や、さらなる検査についても十分に理解した上で検査を受けることをお勧めします。納得のいく検査選びが、不安を和らげ、安心した妊娠生活につながります。
参考文献
※1:Cleveland Clinic, Jun. 2022.※2:Taiwan J Obstet Gynecol., Dec. 2013
※3:Cleveland Clinic, Oct. 2022
※4:Directions., Aug. 2023
国内最安の費用で8項目の遺伝的疾患リスクを検査「新型出生前検査(NIPT)」

お腹の赤ちゃんの遺伝性疾患リスクがわかる
seeDNAの安心サポート
seeDNAは、国際品質規格ISO9001とプライバシー保護のPマークを取得している安心と信頼のDNA鑑定・遺伝子検査の専門機関です。
お腹の赤ちゃんの疾患リスクや親子の血縁関係、パートナーの浮気などにお悩みでしたら、遺伝子検査の専門家が、しっかりとご安心いただけるようサポートいたしますのでお気軽にお問合せください。
【専門スタッフによる無料相談】
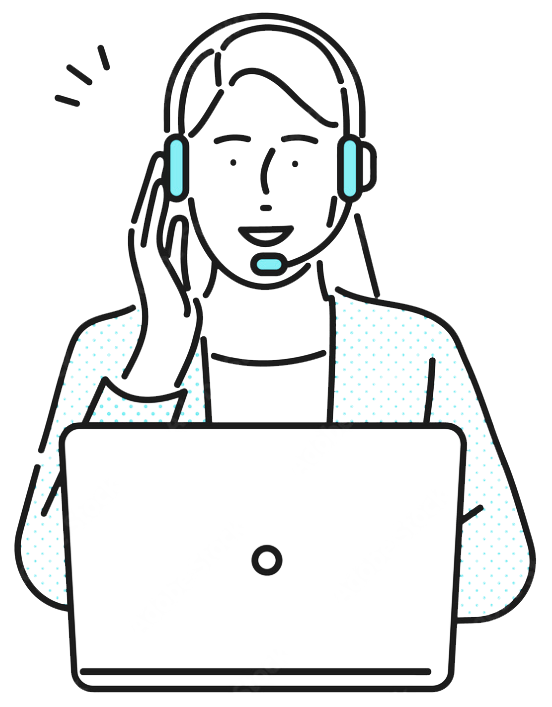
著者
医学博士・医師
広重 佑(ひろしげ たすく)
医学博士、日本泌尿器科学会専門医・指導医、がん治療学会認定医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定産業医、日本抗菌化学療法学会認定医、性感染症学会認定医、Certificate of da Vinci system
Training As a Console Surgeonほか
2010年に鹿児島大学医学部を卒業後、泌尿器科医として豊富な臨床経験を持つ。また、臨床業務以外にも学会発表や論文作成、研究費取得など学術活動にも精力的に取り組んでいる。泌尿器科専門医・指導医をはじめ、がん治療、抗加齢医学、感染症治療など幅広い分野で専門資格を取得。これまで培った豊富な医学知識と技術を活かして、患者様一人ひとりに寄り添った医療を提供している。