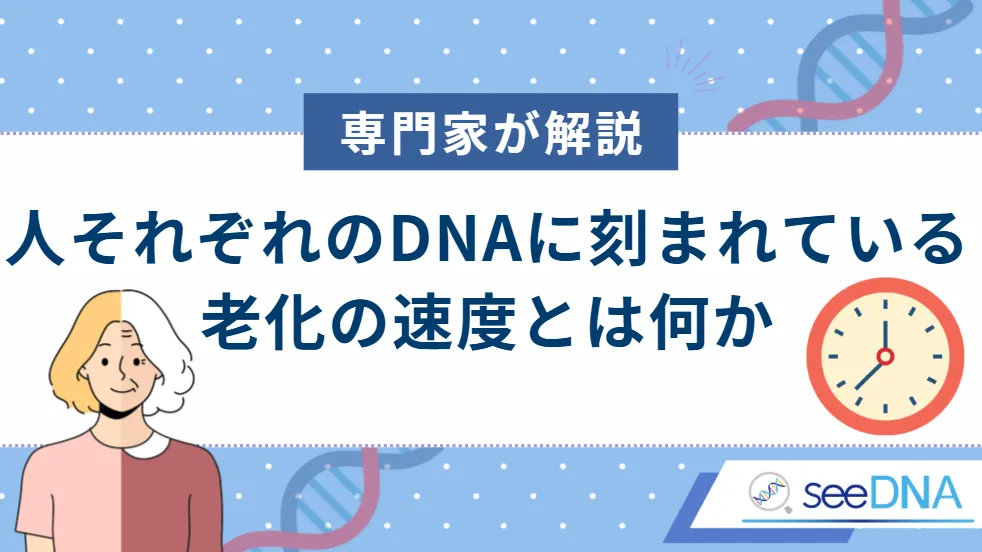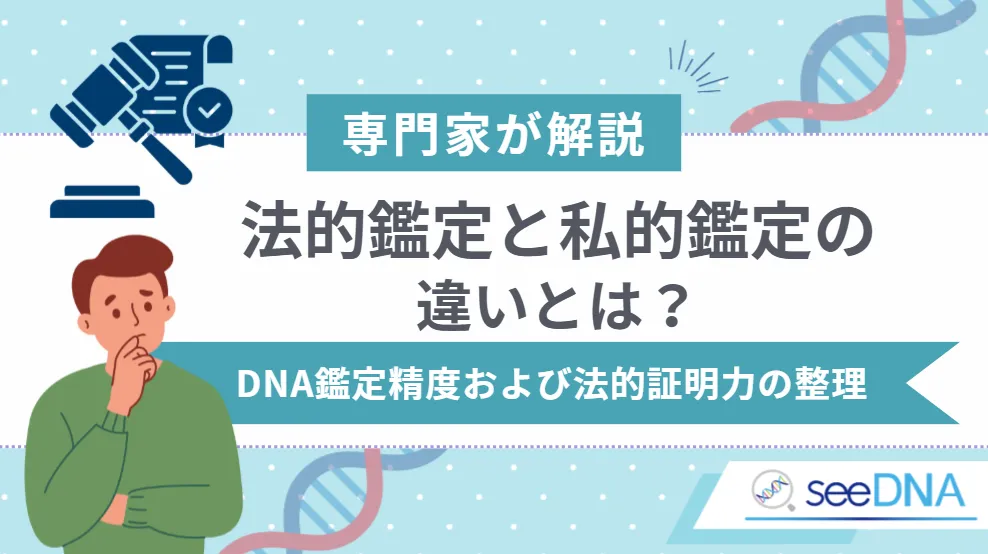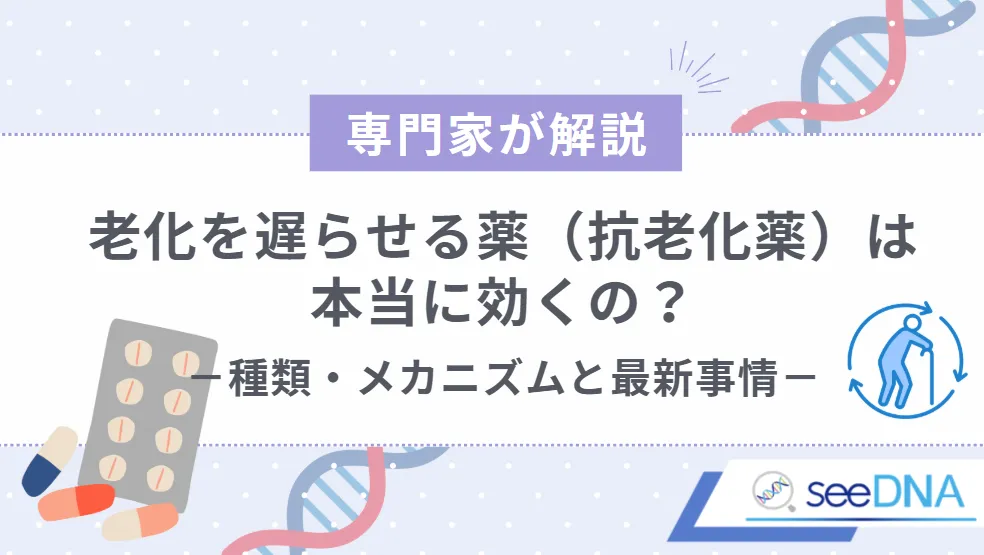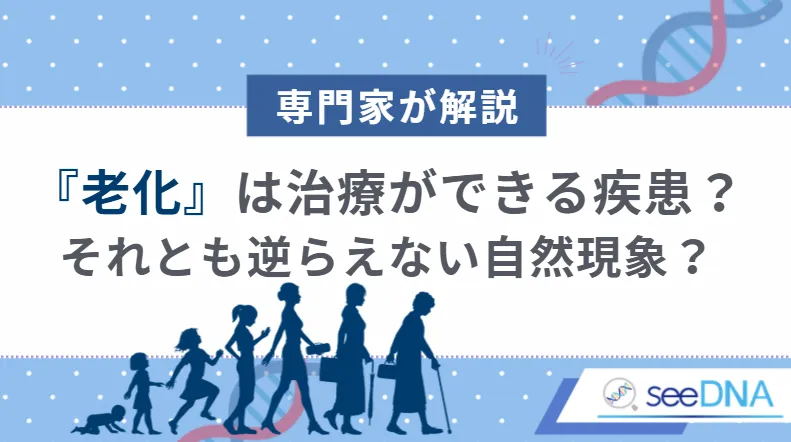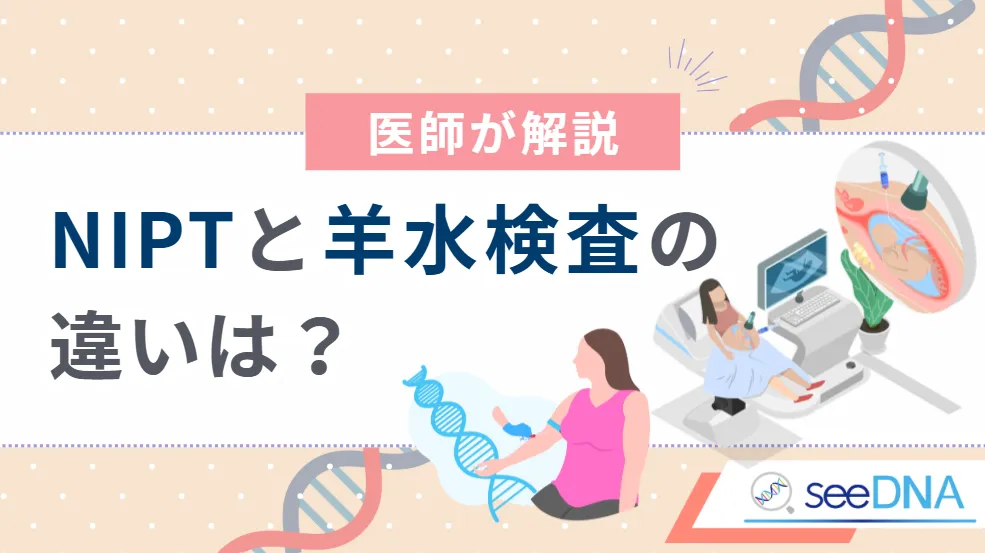科捜研によるDNA鑑定が偽装されても本当に裁判の判決に影響はない?
2025.10.07
佐賀県警から、2012年に採用された40代の技術職員が行った632件のDNA型鑑定のうち2017年以降、7年間で130件で不正があったと発表されました。16件は殺人未遂など重大事件の「証拠として採用」されましたが、検察・県警は「公判(起訴や裁判)への影響はない」との見解をしめしています。「捜査や判決に影響なし」と断言し「再審事案になりうる可能性」も否定されましたが、果たして本当に信用して良いのでしょうか?
ここでは、今までのメディアの報道を整理し、法制度や科学鑑定の実務を踏まえて、「本当に捜査や判決に影響がない」という主張がどこまで説得力を持つかを検証してみます。
報道されている事実
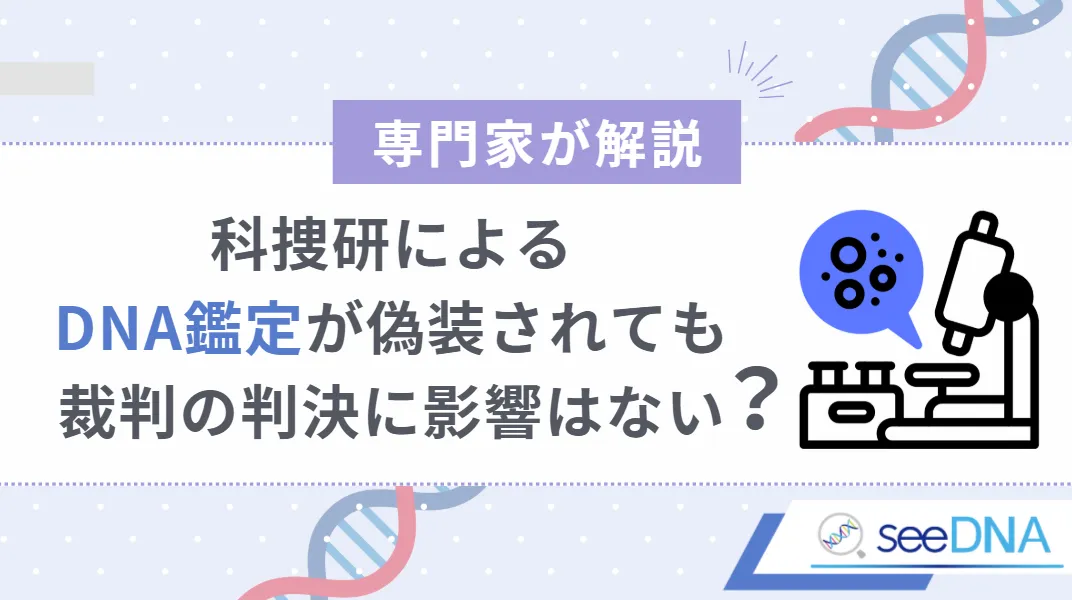
まず、現在報道で明らかになっている点を整理します(すべて確定した法的判断ではなく、報道段階での内容です)。
主な報道内容
- 130件もの不適切なDNA鑑定
佐賀県警の科捜研所属の40代技術職員が、2017年以降7年余りにわたり、実際には鑑定をしていないのに鑑定したように見せかけたり、資料を紛失したり、別のガーゼを返却したり、鑑定記録を偽っていた、という不適切行為が130件確認されたと警察発表。※1 報道では、「DNA鑑定を装った虚偽報告」のケース、「鑑定資料を紛失し代替のものを返却した」ケースなどが挙げられています。※2
この職員は、全体で632件の鑑定を担当しており、そのうち130件で不適切な行為があったという説明もあります。※1 - 16件は重大事件の証拠として使われていた
この中で、16件は殺人未遂などの重大犯罪捜査で証拠として扱われていたという報道があります。※3
ただし、警察はこれら16件について「公判に影響はない」との見解を示しており、「証拠として使われた事例はない」という主張をしているという報道もあります。※4 - 再鑑定で異なる結果が出た事例もある
警察自身の調査で、不正とされた鑑定のうち8件について、再鑑定をしたところ「当初の鑑定結果と異なる結果」が得られたという報道があります。※5
この事実だけでも、「不正分のすべてが結果を変えなかった」と断言することは困難だという見方があります。 - 警察・検察の主張:捜査・公判に影響なし
佐賀県警は「捜査や裁判には支障なかった」「公判に影響するようなケースはなかった」と述べており、検察も「証拠として使われた事例はない」としているという報道があります。※4
ただし、弁護士会や専門家からは「内部調査で終わらせてはならない」「司法制度への信頼が揺らぐ」とする批判も出ています。※6
また、佐賀県警本部長は、第三者委員会を設置しない旨の考えを県議会で示しており、これにも異論が出ています。※4 - 刑事責任を問う可能性
報道段階で、当該職員については「虚偽有印公文書作成罪」「証拠隠滅罪」などの法的責任があり得るという弁護士コメントも報じられています。※7
これらを総合すると、「不正があったこと」はほぼ間違いないと報道されていますが、「それが捜査・判決に実質的な影響を及ぼしたか否か」は、まだ確定的には述べられていません。
科学鑑定・司法制度の観点からの考察

次に、「DNA鑑定」が刑事捜査・裁判で果たす役割、その信頼性、偽造・誤りがあった場合の影響を考えてみます。
DNA鑑定の意義と限界
DNA鑑定は、特に現代の刑事事件で「被疑者と証拠物との遺伝的対応性(マッチング)」を示す有力な科学的証拠として用いられます。被告がそのDNA型と一致するかどうか、あるいは排除できるかどうかを示すものです。
ただし、DNA鑑定にも限界があります:
- 試料の混入、汚染、誤操作、交差反応などが起こり得る。
- 鑑定解釈(例えば、複数人が混ざった試料、微量DNA、部分的アレーなど)には専門的判断が必要であり、必ずしも「完全確定」の証拠ではない。
- 裁判では、鑑定結果はあくまで「証拠の一つ」であり、弁護側が反証や疑義を挙げ得る。
- 科学鑑定機関や鑑定者の信頼性が低ければ、鑑定結果そのものを疑う必要が出てくる。
つまり、DNA鑑定は強力な証拠になり得ますが、絶対無謬(まちがいがない)ではないという前提があります。
偽造・改ざんがあった場合の影響
偽造・改ざん、あるいは鑑定操作ミスがあった場合、以下のようなリスクが生じます:
- 誤判・冤罪リスク
被疑者と無関係のDNA型を偽って提出すれば、被告が有罪とされる可能性があります。
ただし、実際には、DNA鑑定以外にも他の証拠(目撃証言、物的証拠、状況証拠など)が併存することが多いため、DNAだけで判決が決まるケースは限定的です - 再審請求・上訴リスク
すでに有罪判決が確定した事件でも、後日偽造・改ざんが明らかになれば、再審を請求できる可能性があります(刑事訴訟法の制度的枠組みによる)。
偽造が明白であれば、有罪判決の根拠そのものが揺らぐという主張が可能になります。 - 信頼性低下・制度への打撃 鑑定機関や司法制度に対する国民の信頼が損なわれれば、以後の鑑定証拠全体を疑う動きが出てくる可能性があります。これは制度的リスクです。
- 特定事件における無効化・再調査 当該不正が行われた鑑定が証拠として利用された事件においては、裁判所がその鑑定証拠の信用性を否定したり、再鑑定を命じたり、証拠排除(採用を認めない)を行う余地が出てきます。
- 立証責任・反証機会 弁護側が「この鑑定は不正だった可能性がある」と主張すれば、裁判所はその点を検討する義務を負う可能性があります。鑑定過程・鑑定報告書の記録を公開させる、反対鑑定をさせるなどのプロセスが動くこともありえます。
- 部分的には“効力制限”される可能性 不正疑義がある証拠部分だけが排除され、他の正常な鑑定証拠等で判断される、という裁判的な落とし所をとる可能性も考えられます。
“影響なかった”という主張が成り立ちうる条件
警察・検察が「捜査・公判に影響ない」と主張するには、少なくとも次のような条件が必要です:
- 不正鑑定を証拠として用いた事件が存在しない、あるいはそれらの鑑定が事件判断に用いられなかったことが確認できていること。
- 不正とみなされた鑑定の中で、正しい鑑定(再鑑定等)をした結果、元の結論と同一であったことが証明されていること。
- 他の証拠(目撃証言、物証、アリバイ、複数の証拠の整合性など)によって、仮にDNA鑑定を外しても有罪判断が可能であったこと。
- 裁判所が鑑定証拠の信用性を十分チェックしたという記録が残っていること。
これらの条件が確実に満たされていなければ、「影響なし」とする主張は疑問をもたざるを得ません。
報道段階で見える限界と懸念点

報道を見る限り、「捜査・公判に影響なし」という警察側の主張には、少なくとも次のような疑問点があります。
再鑑定で異なる結果が出た例がある
前述のとおり、8件については再鑑定で当初の(不正とされた)鑑定と異なる結果が出たという報道があります。※5
もしこれが正しければ、不正鑑定が誤りを導いた可能性が具体的に示唆されており、「すべて影響がなかった」と断言できなくなります。
「影響なし」の主張の裏付けが不透明
警察・検察側は「影響なし」としていますが、その主張を支える具体的な調査結果、独立性のある検証、第三者の関与、公開性などの説明は、報道段階では十分に見えてきていません。
たとえば、どのような再鑑定をしたか、どの範囲で精査したか、反対鑑定や反証の機会を与えたか、という詳細は報道には出ていません。
また、報道では、佐賀県警本部長が「第三者委員会を設置しない」という答弁をしており、透明性・公平性を担保する外部調査を拒む意向も示しているという指摘もあります。※4
そもそも不正の全貌が明らかではない
130件という数自体は大きく、どの不正鑑定がどのような事件に使われたか、その鑑定が素材的に決定的かどうか、どの程度事件判断に依存していたかなど、個別ケースの詳細が報道では不足しています。
不正鑑定が行われた事件のうち、公判・判決に使われたものがどれだけあるか、その中で鑑定が決定的だったものがあるかどうか、という精査がまだ不透明です。
再審請求・将来の検証可能性
たとえ現時点で「影響なし」と判断されていても、不正が明らかになった以上、過去の判決・事件に対して再審請求や補償請求がなされる可能性は残ります。司法制度上、そのような請求は法的に想定される制度です。
科学鑑定全体の信頼性低下
今回のような事件は、DNA鑑定のみならず、他の科学鑑定手法(指紋、鑑識、化学分析など)に対しても疑義を呼ぶ可能性があります。つまり、この1件の不祥事が、“鑑定証拠全体への信頼”を揺るがす悪影響を及ぼす可能性があります。
不正やミスを防ぐためのseeDNA遺伝医療研究所の取り組み
まとめ

現時点で「影響なし」とする主張を鵜呑みにするのは危険であり、以下のような見方が妥当だと考えられます。
- この事件の不正性は極めて重大であり、仮に影響がなかったとしても、判断可能性が疑われる余地があります。
- 「影響なし」とする主張を信じるには、それを裏付ける十分な透明性・第三者検証・再鑑定結果などの説明が不可欠です。
- 過去の判決・事件のうち、当該不正鑑定が証拠として利用されたものについては、事後検証・再審請求がなされる可能性があります。
- 今後の対応(第三者委員会、全鑑定書の点検、鑑定プロセスの見直し・公開化など)が、司法制度全体の信頼回復に不可欠でしょう。
【参考文献】
※1:朝日新聞※2:朝日新聞
※3:FNNプライムオンライン
※4:まとめダネ!FNNプライムオンライン
※5:TBS NEWS DIG
※6:FNNプライムオンライン
※7:Livedoor News+FNNプライムオンライン
seeDNA遺伝医療研究所の安心サポート
seeDNA遺伝医療研究所は、国際品質規格ISO9001とプライバシー保護のPマークを取得している安心と信頼のDNA鑑定・遺伝子検査の専門機関です。
お腹の赤ちゃんの親子の血縁関係や疾患リスク、パートナーの浮気などにお悩みでしたら、遺伝子検査の専門家が、しっかりとご安心いただけるようサポートいたしますのでお気軽にお問合せください。
【専門スタッフによる無料相談】
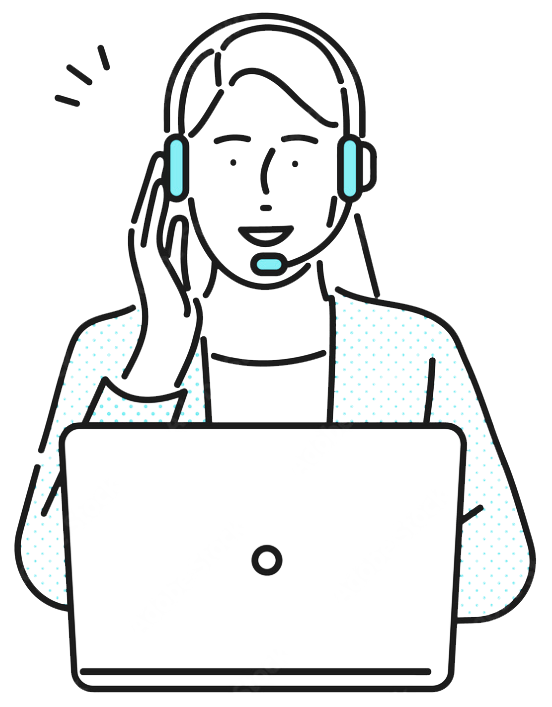
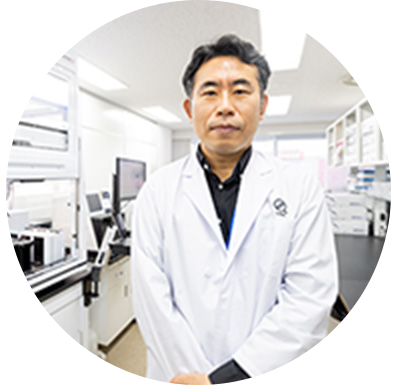 著者
著者
医学博士 富金 起範
筑波大学、生体統御・分子情報医学修士/博士課程卒業
2017年に国内初となる微量DNA解析技術(特許7121440)を用いた出生前DNA鑑定(特許7331325)を開発