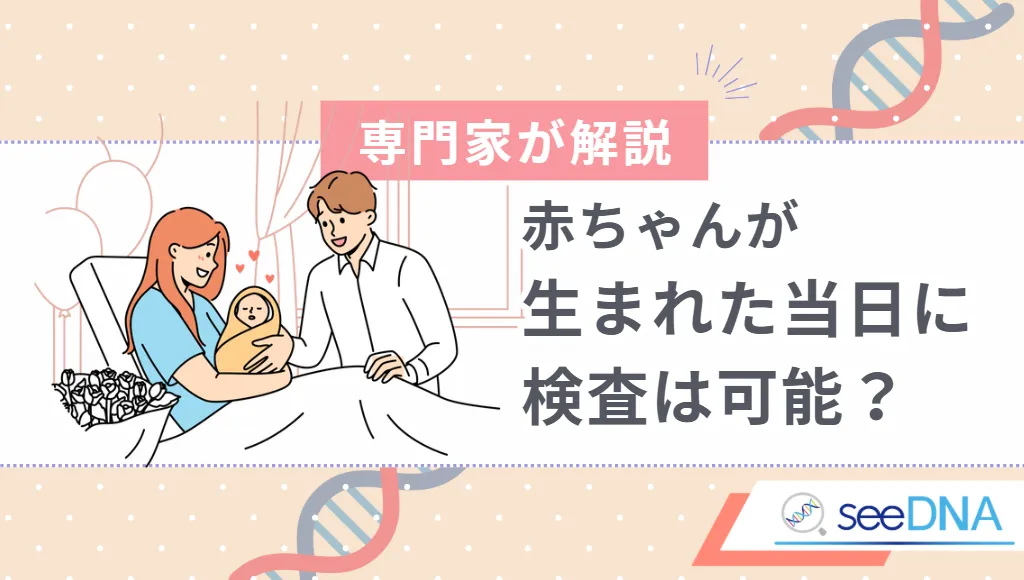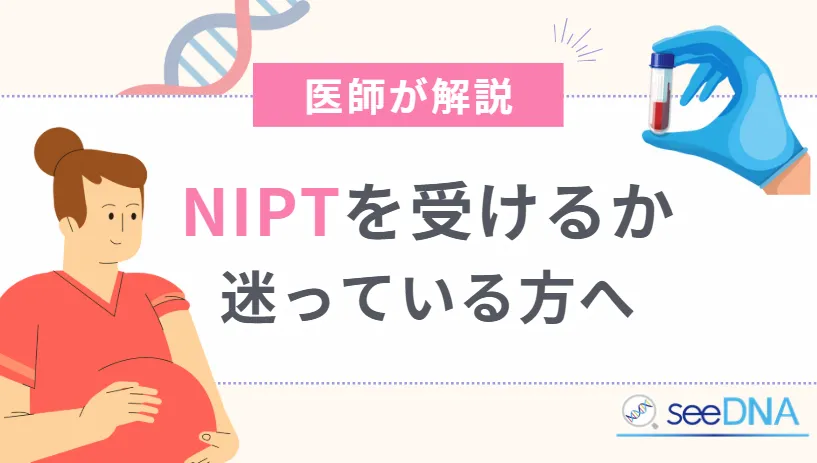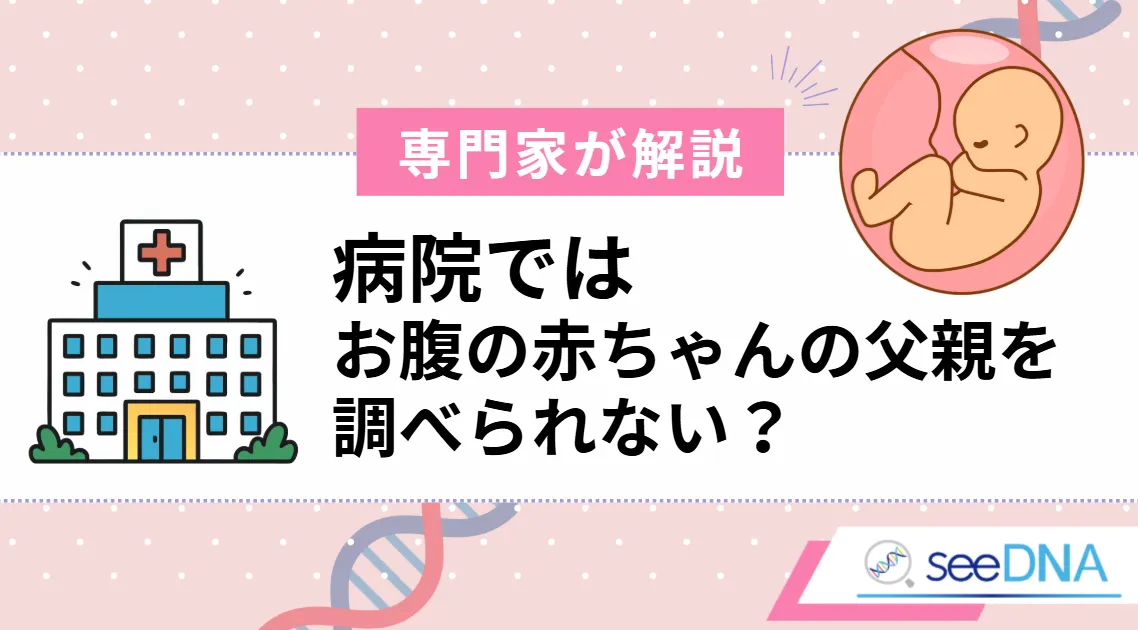確定診断のリスクはどれぐらいですか?
2025.10.06
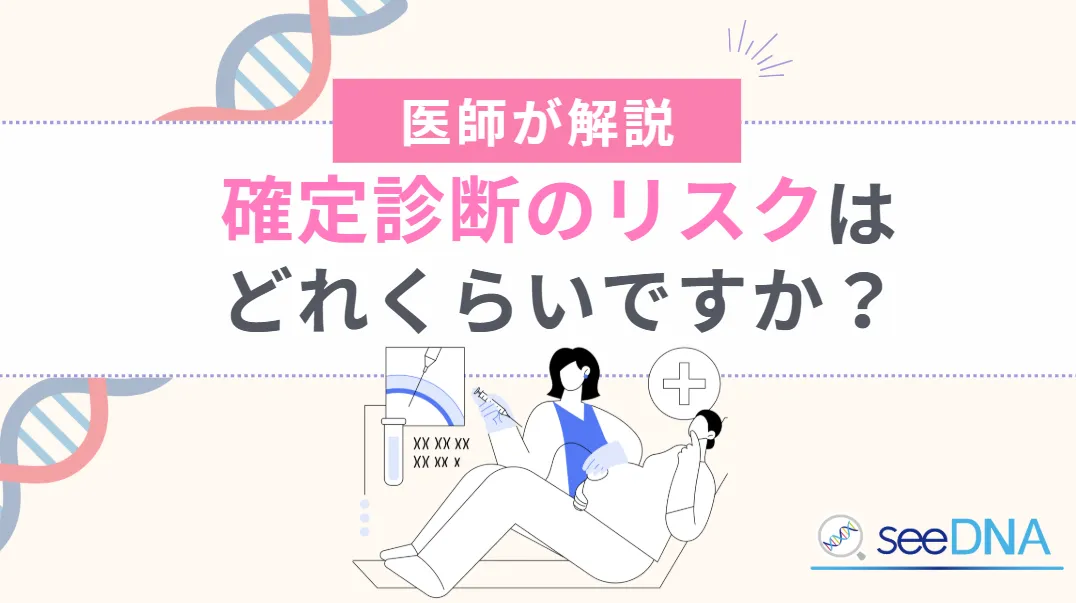
妊娠中に赤ちゃんの健康状態をより正確に知りたいと考えたとき、多くの方が「確定診断」にあたる羊水検査や絨毛検査という選択肢を耳にされることでしょう。
これらは出生前検査の中でも精度が高く、染色体異常や遺伝子疾患の有無を直接確認できる重要な検査です。
しかし、精度が高い一方で、妊婦さんやご家族が最も心配されるのが「リスク」ではないでしょうか。
本記事では、羊水検査と絨毛検査に伴う流産や合併症のリスクについてわかりやすく解説します。実際の数字やリスクの内容を正確に知ることが、安心して検査を選択する第一歩となります。
羊水検査のリスク

羊水検査は、妊娠15週以降に行われる確定診断法です。お母さんのお腹に超音波で位置を確認しながら細い針を刺し、胎児を包んでいる羊水を少量採取します。その羊水を調べることで、染色体の異常や遺伝子疾患の有無を詳しく調べることができます。
流産のリスク
羊水検査で最も注意すべきリスクは流産です。
2019年の研究によると、検査によって流産リスクは約0.3%と報告されています。※1
一方、別の研究では、そのリスクは約0.1%とされています。※2
その他の合併症
流産以外の合併症として、以下が報告されています:
- 感染症
羊水検査のあとに子宮内感染(絨毛膜羊膜炎など)が起こる可能性があります。
ただし、国際産婦人科超音波学会(ISUOG)のガイドラインでは、そのリスクは0.1%未満とされており、適切に清潔操作を行えばほとんど防ぐことができます。※3 - 羊水漏れ
検査後に羊水が少し漏れることがあり、頻度は約1~2%です。※3
多くは自然に止まりますが、まれに持続すると流産の原因になることもあります。なお、同じ週数で自然破水が起こった場合と比べると、流産リスクは低いとされています。※3 - 胎児への直接的損傷
超音波検査を併用せずに針を刺した場合、ごくまれに胎児が傷つくことがあります。
報告例としては、眼の外傷、皮膚や腱の損傷、血管の損傷、さらには脳の損傷などがありますが、近年では、超音波で胎児の位置を確認しながら行うのが一般的であるため、発生は極めて稀です。※3
絨毛検査のリスク

絨毛検査は妊娠10~14週頃に実施される確定診断法です。胎盤の一部である絨毛を採取して、染色体の異常や遺伝子疾患の有無を詳しく調べます。羊水検査よりも早期に実施できるという利点があります。アプローチ方法には、腹部から針を刺入する経腹法と、膣から器具を挿入する経膣法があります。
流産のリスク
絨毛検査においても最も注意すべきリスクは流産です。
2019年の研究によると、検査によって流産リスクは約0.2%と報告されています。※1
また、別の報告でも約0.22%とほぼ同様の報告がされています。※2
絨毛検査特有のリスク
- 胎児四肢欠損
妊娠9週以前に検査を行った場合、胎児の手足に欠損が生じるリスクがわずかに高まるとされています。とはいえ、これは非常に稀であり、妊娠10週以降に検査を実施することでリスクは大きく下げられます。※4 - 母体出血
経膣法で検査を行うと、一時的に少量の出血が見られることがあります。多くは自然に止まりますが、抗凝固薬を使用している方では出血リスクがやや高くなる可能性があります。※4 - 感染症
検査後の感染症リスクは0.5%未満と非常に低いとされています(4)。ただし、母体がHIVや肝炎などの血液感染症を持っている場合、母子感染(垂直感染)のリスクについて十分に説明を受ける必要があります。※4 - Rh不適合
血液型が不一致(母体がRh陰性、胎児がRh陽性)の場合、検査により血液が混じることで胎児溶血性疾患が起こる可能性があります。このため、Rh不適合は相対的な禁忌と考えられています。※4
アプローチ方法による違い
経腹法と経膣法では、それぞれで起こりうる合併症には多少違いがありますが、大きなリスクの差はないと報告されています。※2
実際には、胎盤の位置やお母さんの体の状態に合わせて、医師がより安全な方法を判断して選びます。
限局性胎盤モザイク
絨毛検査には、限局性胎盤モザイク(胎盤と赤ちゃんの遺伝情報が一部異なる状態)という特有の問題があります。これは全体の約1~2%程度で起こる可能性があるとされています。※4
限局性胎盤モザイクとは…
本来、胎盤と赤ちゃんは同じ受精卵からできるため、同じ染色体の情報を持つはずです。しかし、発育の過程で胎盤の一部だけに染色体の異常が起こることがあり、この場合は検査では「異常あり」と出ても、赤ちゃん自体は正常というケースがあります。
まれに、胎盤には異常がなくても、赤ちゃんの方に染色体異常があるケース(真のモザイク)もあります。これは約10%程度の頻度で報告されています。※4
もし絨毛検査で不一致の可能性が疑われる場合は、妊娠中期に羊水検査で再確認が行われることがあります。
多胎妊娠でのリスク
双子以上の妊娠では、そうでない場合より合併症のリスクが少し高い傾向があると報告されています。ただし、その差は統計的に明らかでないことも多く、熟練した医師が適切な方法で行えば安全に実施できることが、最新の研究で示されています。※5
まとめ

羊水検査と絨毛検査は、どちらも胎児の染色体や遺伝子を直接調べることができる確定診断法であり、高い診断精度を持つ一方で、流産や感染といった一定のリスクを伴います。
近年の大規模研究により、そのリスクは従来よりも低いことが示されていますが、「ゼロ」ではありません。また、検査時期や胎盤の位置、多胎妊娠といった条件によっても合併症の可能性は変化します。
大切なのは、メリットとリスクを正しく理解した上で、ご自身やご家族にとって最適な選択をすることです。本記事が、検査を検討される皆さまの不安を和らげ、納得のいく選択につながる一助となれば幸いです。
\妊娠中の赤ちゃんとお母さんに安全なNIPT/
seeDNA遺伝医療研究所の安心サポート
seeDNA遺伝医療研究所は、国際品質規格ISO9001とプライバシー保護のPマークを取得している安心と信頼のDNA鑑定・遺伝子検査の専門機関です。
お腹の赤ちゃんの疾患リスクや親子の血縁関係、パートナーの浮気などにお悩みでしたら、遺伝子検査の専門家が、しっかりとご安心いただけるようサポートいたしますのでお気軽にお問合せください。
【専門スタッフによる無料相談】
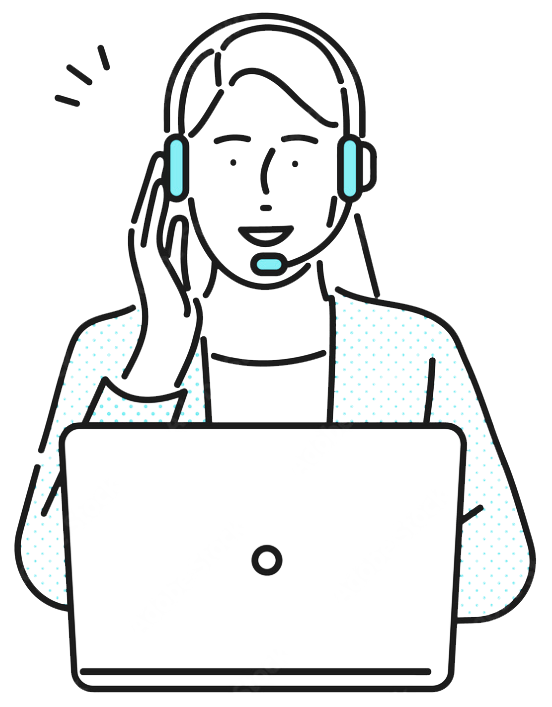
【参考文献】
※1:Ultrasound Obstet Gynecol. 2019 Oct※2:Ultrasound Obstet Gynecol. 2015 Jan
※3:Ultrasound Obstet Gynecol. 2016 Aug
※4:StatPearls [Internet]. 2025 Jan
※5:Ultrasound Obstet Gynecol. 2020 Nov
著者
医学博士・医師
広重 佑(ひろしげ たすく)
医学博士、日本泌尿器科学会専門医・指導医、がん治療学会認定医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定産業医、日本抗菌化学療法学会認定医、性感染症学会認定医、Certificate of da Vinci system
Training As a Console Surgeonほか
2010年に鹿児島大学医学部を卒業後、泌尿器科医として豊富な臨床経験を持つ。また、臨床業務以外にも学会発表や論文作成、研究費取得など学術活動にも精力的に取り組んでいる。泌尿器科専門医・指導医をはじめ、がん治療、抗加齢医学、感染症治療など幅広い分野で専門資格を取得。これまで培った豊富な医学知識と技術を活かして、患者様一人ひとりに寄り添った医療を提供している。