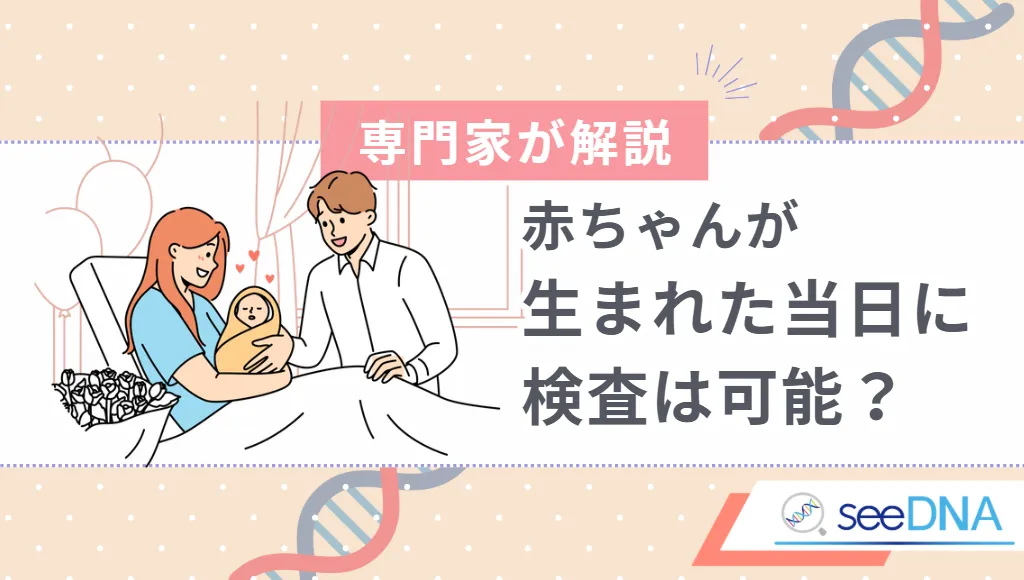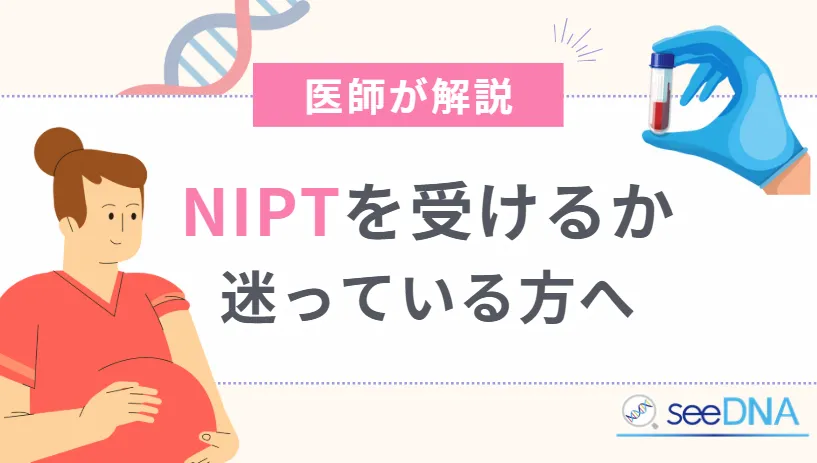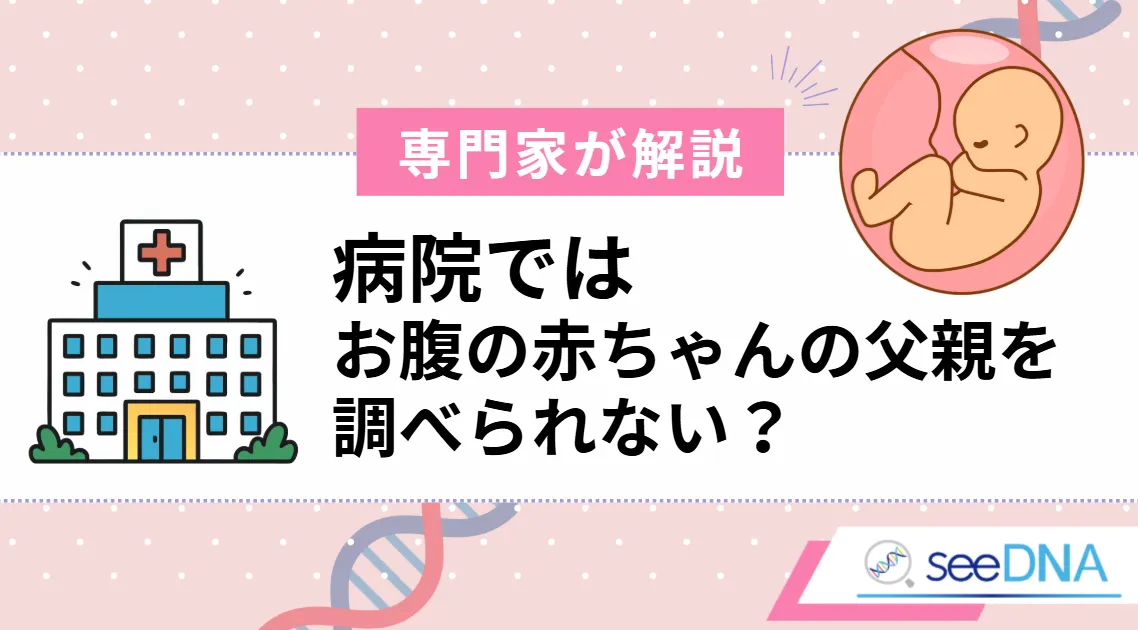【専門家が解説】NIPTの精度はなぜ「年齢」と「疾患」で変わるの?
2025.10.15
NIPT(新型出生前検査)は、母体血中の胎盤由来DNAを解析して、胎児の染色体数的異常の可能性を推定する“スクリーニング検査”です。結果は「診断」ではなく確率情報であり、陽性時は羊水検査などで確定します。日本の公的資料でもこの位置づけが明確に示されています。
年齢で「陽性的中率(PPV)」が変わる理由
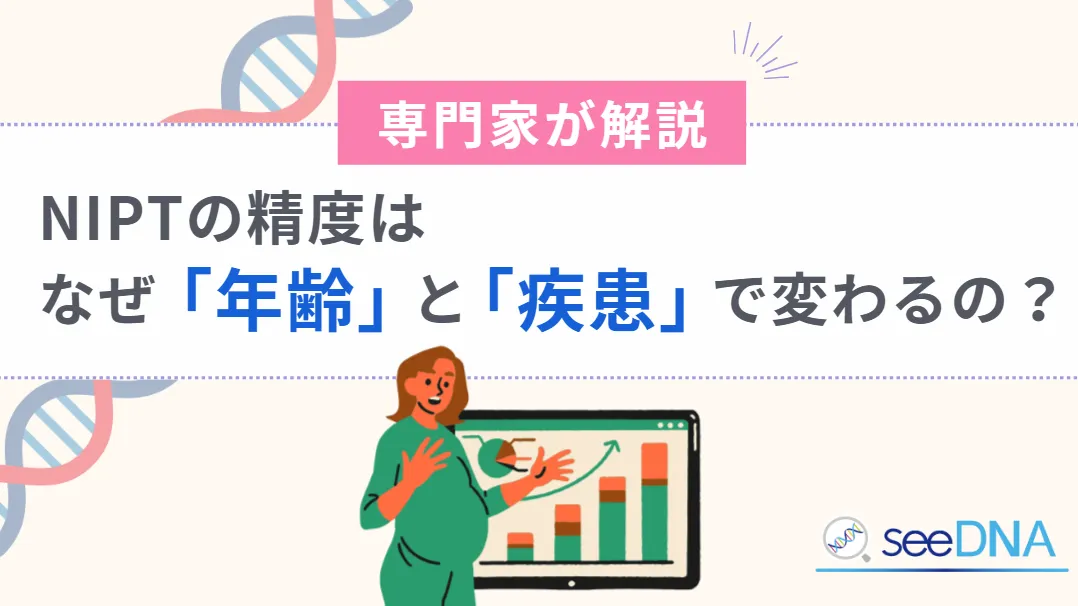
同じ検査性能(感度・特異度)でも、PPV=“陽性のとき本当に当たっている確率”は集団の有病率(事前確率)で大きく変わります。母体年齢が上がるとT21などの有病率は上がるため、高年齢ではPPVが高く、若年では低くなる傾向があります。
海外ガイドラインでも「cfDNA検査はスクリーニングであり、PPV/NPVは有病率に依存」と明記されており、カウンセリング時にこの点を丁寧に説明するよう求めています。
疾患ごとに精度が違う理由

胎児由来DNAの割合(fetal fraction: FF)
NIPTは、母体血中に含まれている「胎児由来DNAの割合(FF)」が一定以上ないと性能が落ち、判定不能(no-call)や偽陰性のリスクが増します。FFは妊娠週数・母体BMIなどの影響を受け、FFが低いほど誤差が増えやすいことが大規模解析で示されています。さらにT13/T18ではFFが相対的に低くなりがちで、T21より検出成績が劣る傾向も報告されています。
胎盤限局性モザイク(CPM)
cfDNAの主な供給源は胎盤です。胎盤にだけ異常があり胎児は正常というCPMがあると、偽陽性となることがあります。CPMの関与はT13/T18や性染色体異常で相対的に目立ち、疾患間でPPVが違う主要因の一つと整理されています。
よくある誤差要因(消失双胎・母体要因・技術要因)
- 消失双胎(vanishing twin)
早期に消失した胎児のDNAが母体血に残ると、もう一方の胎児は正常でも陽性という結果が出る時があります。多胎で消失双胎や一児の異常が分かった場合、cfDNAは不正確になりやすいため、診断的検査の提示が推奨されています。 - 母体要因(稀)
未診断の悪性腫瘍があると、複数染色体にまたがる異常パターンとしてNIPTに表れることがあります。2015年の古典的報告以降、異常パターンで判明する症例が継続的に報告され、最近の研究でも整合的です。 - 技術・検体要因
ライブラリ作成・読長・解析手法の違い、極端な低FF(多くは4%未満)などで、判定不能・誤判定が増えます。
実務の読み方:結果にどう向き合うか

- 陽性=確定ではない
NIPTはあくまでもスクリーニング検査であるため、陽性なら羊水検査/CVSで確定するのが原則です。疾患ごとにPPVは異なり(概ねT21>T18>T13)、年齢・超音波所見・既往などの事前確率で上下します。 - 陰性でもゼロではない
FFが低い・超音波で強い所見がある等では、陰性でも追加評価が必要です。判定不能(no-call)はそれ自体が異数性リスク上昇と関連する報告もあり、再採血や確定検査の相談を行うことを推奨します。 - 多胎・消失双胎・特殊状況では慎重に
消失双胎や胎児の一児異常が判明している多胎では、cfDNAの不正確リスクが高いため、診断的検査の提示を前提にカウンセリングを。 - カウンセリングは“ベイズの橋渡し”
PPV/NPV、有病率、FF、超音波所見をひとつの物語として接続して伝えることが重要です。海外ガイドラインは検査前後の説明を重視し、国内でも公的資料がスクリーニングの性格を明示しています。
まとめ

- 年齢で精度が変わる主因は、検査そのものではなくPPVを左右する有病率。高年齢ほどPPVは上がり、若年では下がる。
- 疾患差の主因はFFと胎盤側の生物学(CPM)。一般にT21が最も安定、T18、T13の順でPPVが下がりやすい。
- 消失双胎・母体腫瘍・低FFなどで偽陽性/判定不能が起き得る。状況に応じて再採血や確定検査を組み合わせる。
- 日本ではNIPTは「診断ではない」スクリーニングとして運用され、陽性→確定検査という流れが基本。迷ったら遺伝カウンセリングが必要。
\お腹の赤ちゃんの遺伝性疾患リスクがわかる/
【参考文献】
厚生労働省「母体血を用いた出生前遺伝学的検査(NIPT)に関する指針」(Ministry of Health, Labour and Welfare)厚生労働省「NIPTワーキンググループ(第4回)資料」(Ministry of Health, Labour and Welfare)
ACOG「Current ACOG Guidance(NIPTの位置づけ・多胎での注意)」(ACOG)
ACOG「Practice Bulletin/Committee Opinion(PPV/NPVの説明)」(ACOG+1)
AJOGレビュー「偽陽性の起源:胎盤・母体・胎児・技術要因(CPM/消失双胎など)」(ScienceDirect)
Frontiers in Pediatrics 2023「FFに影響する因子とT21/18/13の関係」(Frontiers)
Bianchiら, JAMA 2015「NIPTで判明した母体悪性腫瘍」+近年の追試(JAMA Network+1)
seeDNA遺伝医療研究所の安心サポート
seeDNA遺伝医療研究所は、国際品質規格ISO9001とプライバシー保護のPマークを取得している安心と信頼のDNA鑑定・遺伝子検査の専門機関です。
お腹の赤ちゃんの親子の血縁関係や疾患リスク、パートナーの浮気などにお悩みでしたら、遺伝子検査の専門家が、しっかりとご安心いただけるようサポートいたしますのでお気軽にお問合せください。
【専門スタッフによる無料相談】
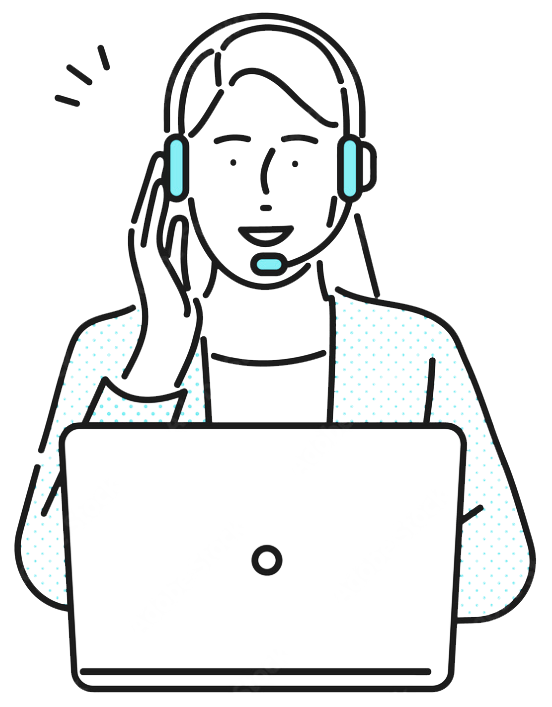
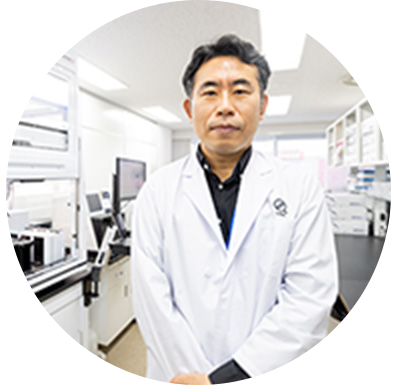 著者
著者
医学博士 富金 起範
筑波大学、生体統御・分子情報医学修士/博士課程卒業
2017年に国内初となる微量DNA解析技術(特許7121440)を用いた出生前DNA鑑定(特許7331325)を開発