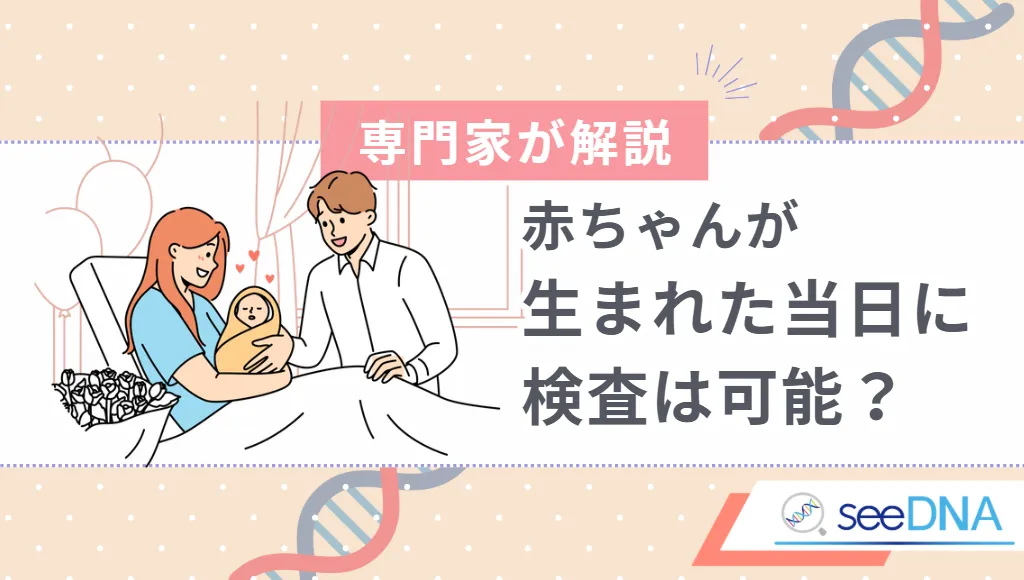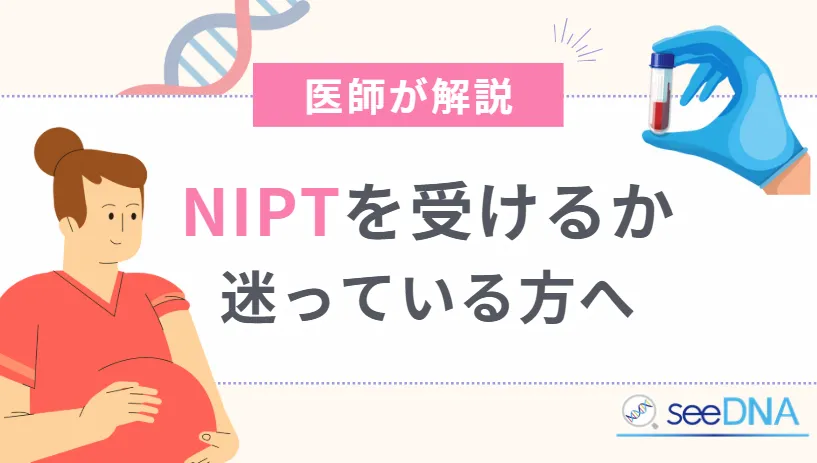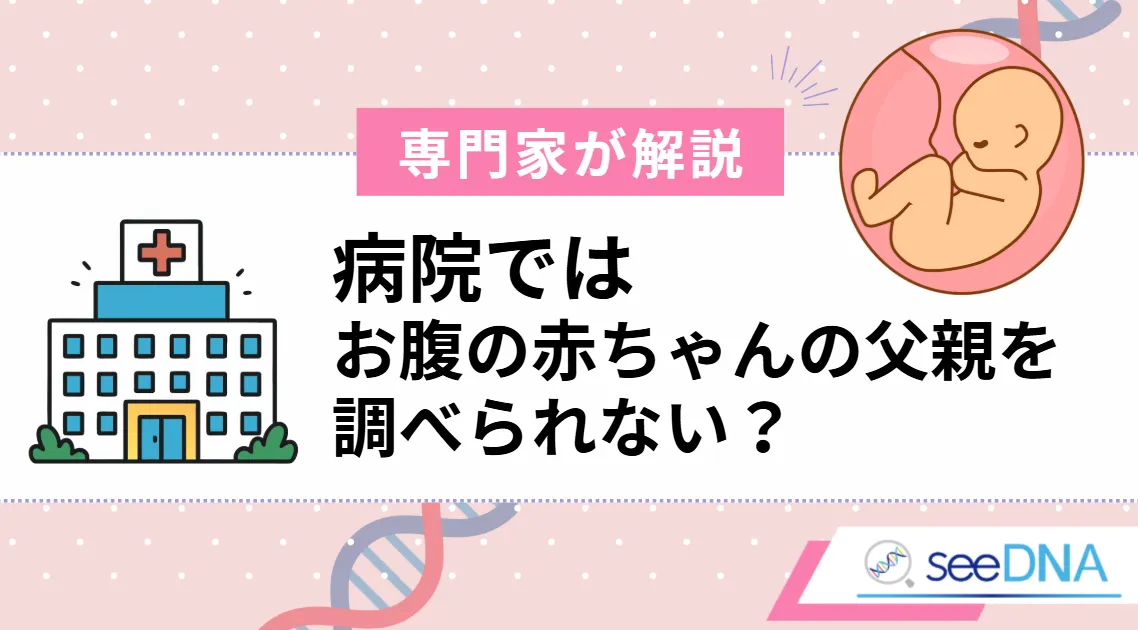【専門家が解説】NIPT陽性の背景と確定診断の必要性
2025.10.16
非侵襲性出生前遺伝学的検査(NIPT)は、母体血中の胎児由来DNAを解析して染色体異常の可能性を評価するスクリーニング検査です。しかし、NIPTで「陽性(異常の可能性あり)」と判定されても、それが確定診断を意味するわけではありません。
この段階で重要なのは、確定診断につながる検査法とその特徴・リスクを理解したうえで、医師や遺伝カウンセラーと慎重に話し合うことです。
本記事では、NIPTで陽性となった場合に選択肢となる確定診断(絨毛検査・羊水検査およびマイクロアレイ解析など)の違いを、見出し付きで整理して解説します。
確定診断とは何か?

スクリーニング検査と確定診断の違い
- スクリーニング検査(ふるい分け検査):異常の可能性を評価するもので、偽陽性・偽陰性の可能性がある
- 確定診断(侵襲的検査):胎児または胎盤組織を直接採取して染色体や遺伝子を解析し、より正確な判定を行う
NIPTで陽性の時点では、あくまで「可能性が高い」という段階であり、確定診断を経てようやく正確な診断結果が得られます。
確定診断の方法:種類別解説

代表的な確定診断法とその解析法を、特徴・リスク・適用時期を交えて整理します。
絨毛検査(CVS:Chorionic Villus Sampling)
■実施時期と採取対象
・妊娠 10~13週頃 が一般的な実施時期
・採取対象は 絨毛(胎盤になる組織の一部)
■解析方法と検出可能範囲
・通常の染色体解析(Gバンド法、FISH 法など)
・マイクロアレイ解析(CMA/SNP アレイ)を併用することも可能
・微小な欠失・重複変異(Copy Number Variant: CNV)も検出できる可能性あり(ただしすべてが検出できるわけではない)
■リスクおよび注意点
・流産リスク:経腹法でおおよそ 0.2 % 程度とされる報告あり
・絨毛には胎盤性モザイク(Placental mosaicism)の可能性があり、絨毛検査で異常が出ても、実際の胎児は正常な場合もある
・早期に検査できる反面、誤差の可能性や適用施設の制限も考慮が必要
羊水検査(Amniocentesis)
■実施時期と採取対象
・妊娠 15週以降 に行うのが原則
・採取対象は 羊水 中に漂う胎児由来細胞
■解析方法と検出可能範囲
・Gバンド染色体解析、FISH 法
・必要時にはマイクロアレイ解析を併用
・染色体数的異常、構造異常、ある程度の微小な変異を検出可能
■リスクおよび注意点
・流産・死産リスク:一般的に約 0.1~0.3 %と報告される
・出血・子宮収縮誘発・破水・感染などの合併症も稀に発生する可能性
・安定性と精度のバランスが比較的良い選択肢
染色体マイクロアレイ解析(CMA/SNP アレイ)
■概要と原理
・マイクロアレイ法は、全ゲノムを対象に**コピー数変異(CNV)**を検出する手法で、従来法で見逃されがちな微小な染色体異常を捉えられる可能性があります。
・日本産科婦人科学会も「染色体マイクロアレイ検査の利用上の留意点」を公表しており、適用や解釈には注意を要します。
■適用場面と利点
・胎児に構造異常(超音波異常など)が認められる場合には、追加の遺伝学的情報として活用されることがある
・従来の染色体解析では検出できない、微小な欠失・重複変異の発見につながる可能性
・ただし、均衡型再構成(相互転座・逆位など)は検出できない点に注意が必要
■課題と注意点
・意義不明(VOUS:Variant of Uncertain Significance)な変異が見つかる可能性
・解釈が難しく、妊婦・家族への説明が重要
・実施できる施設が限定されていることが多い
・マイクロアレイ染色体検査実施時には、ガイドラインや関連学会の指針に基づいた対応が求められる
比較表:確定診断法まとめ
| 検査法 | 実施時期 | 採取対象 | 主な解析法 | 検出可能範囲 | リスク | 長所 | 欠点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絨毛検査 | 妊娠10?13週 | 絨毛 | Gバンド、FISH、マイクロアレイ | 染色体数・構造異常、微小CNV | 流産リスク約0.2%、胎盤モザイクあり | 早期実施可能、早めに結果入手可能 | モザイク誤差、流産リスク、施設制限 |
| 羊水検査 | 妊娠15週以降 | 羊水中細胞 | Gバンド、FISH、マイクロアレイ | 染色体異常、構造異常、微小変異 | 流産リスク0.1~0.3%、破水・感染など | 比較的精度・安全性バランス良好 | 実施可能時期がやや限られる、検査結果待ち時間 |
| マイクロアレイ解析 | 上記検体を利用 | 絨毛または羊水 | マイクロアレイ(CNV検出) | 微小な欠失や重複変異 | 解釈困難な変異の発見可能性 | より精密な遺伝情報取得可能 | VOUSの解釈、実施施設の制限、均衡型変異の検出不可 |
(表は簡略化した比較で、実際の適用は施設や検査内容により異なります)
選択時の判断基準と注意点

確定診断を選ぶ際には、以下のポイントを考慮して判断することが重要です。
- 妊娠週数:早期に結果を知りたいか、リスクを下げたいかで適した検査法が変わる
- 施設の体制:検査が可能かどうか、マイクロアレイ実施設備の有無
- リスク許容度:流産リスクや検査合併症の可能性をどう考えるか
- 情報の深さ:単に主要染色体異常を知りたいか、微小変異まで知りたいか
- 説明と同意:遺伝カウンセリングや検査前後の説明体制が整っているか
日本では、NIPT や出生前検査の実施体制・情報提供体制の整備が進められており、厚生労働省およびこども家庭庁などでガイドラインや報告書が公表されています。
たとえば、厚生労働省の「NIPT 等の出生前検査に関する専門委員会」に関する報告書があります。また、厚生労働省・こども家庭庁の情報提供や認証制度の方針も参考になります。
まとめ:安心して進めるために

NIPT の陽性結果は、あくまで「可能性を示すサイン」です。確定診断には 絨毛検査・羊水検査・マイクロアレイ解析 といった方法があり、それぞれに特徴・利点・リスクがあります。
時間・安全性・精度・説明体制などを考慮しながら、専門家と相談して適切な選択をすることが大切です。
検査を検討・実施する際には、以下の点を確認しておくと良いでしょう:
- 遺伝カウンセリングを受けられる体制があるか
- 検査施設の実績と設備
- リスクと検査結果までの時間
- 検査費用(出生前診断は保険適用外の場合がほとんど)
適切な情報と支援のもとで、負担を軽くしながら決断を進められるよう心から願っています。
\お腹の赤ちゃんの遺伝性疾患リスクがわかる/
【参考文献】
厚生労働省「出生前検査専門委員会報告書」日本産科婦人科学会「染色体マイクロアレイ検査の利用上の留意点」
慶應義塾大学臨床遺伝学センター「マイクロアレイ検査ガイダンス」
こども家庭庁「出生前検査情報サイト」
seeDNA遺伝医療研究所の安心サポート
seeDNA遺伝医療研究所は、国際品質規格ISO9001とプライバシー保護のPマークを取得している安心と信頼のDNA鑑定・遺伝子検査の専門機関です。
お腹の赤ちゃんの親子の血縁関係や疾患リスク、パートナーの浮気などにお悩みでしたら、遺伝子検査の専門家が、しっかりとご安心いただけるようサポートいたしますのでお気軽にお問合せください。
【専門スタッフによる無料相談】
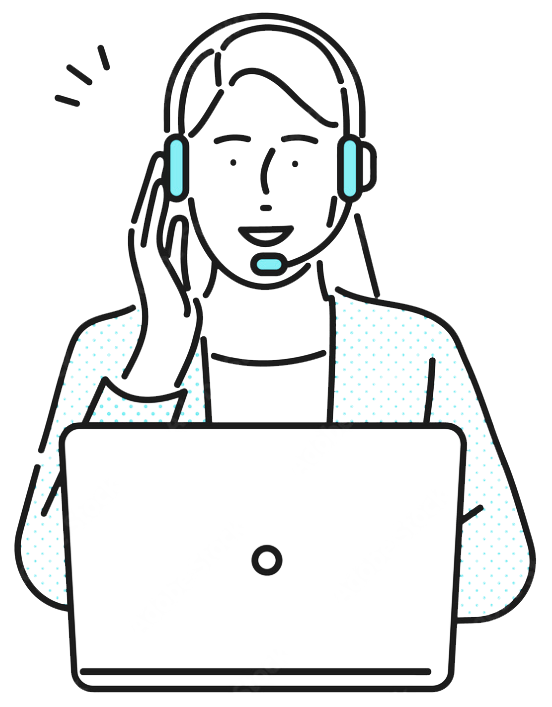
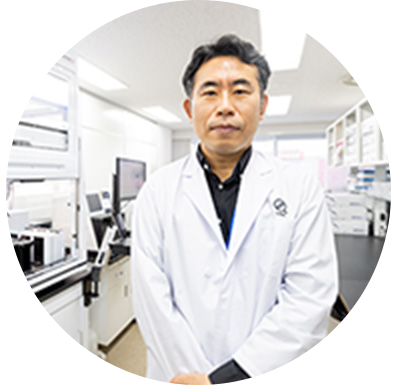 著者
著者
医学博士 富金 起範
筑波大学、生体統御・分子情報医学修士/博士課程卒業
2017年に国内初となる微量DNA解析技術(特許7121440)を用いた出生前DNA鑑定(特許7331325)を開発