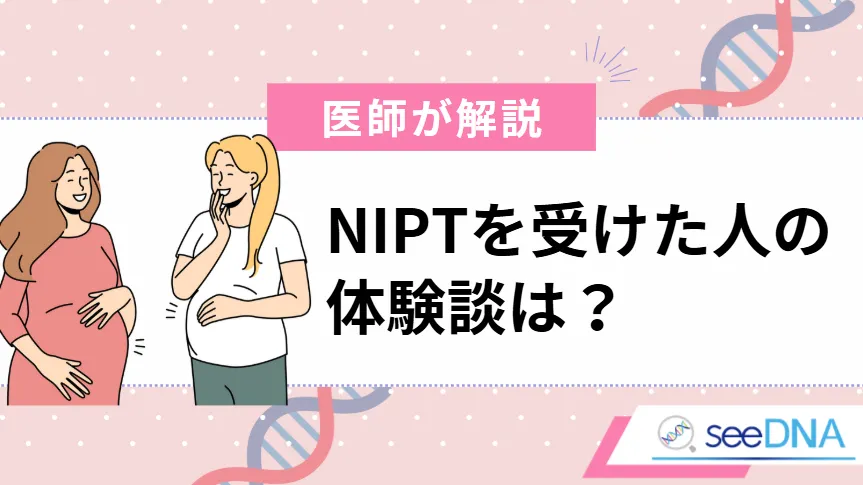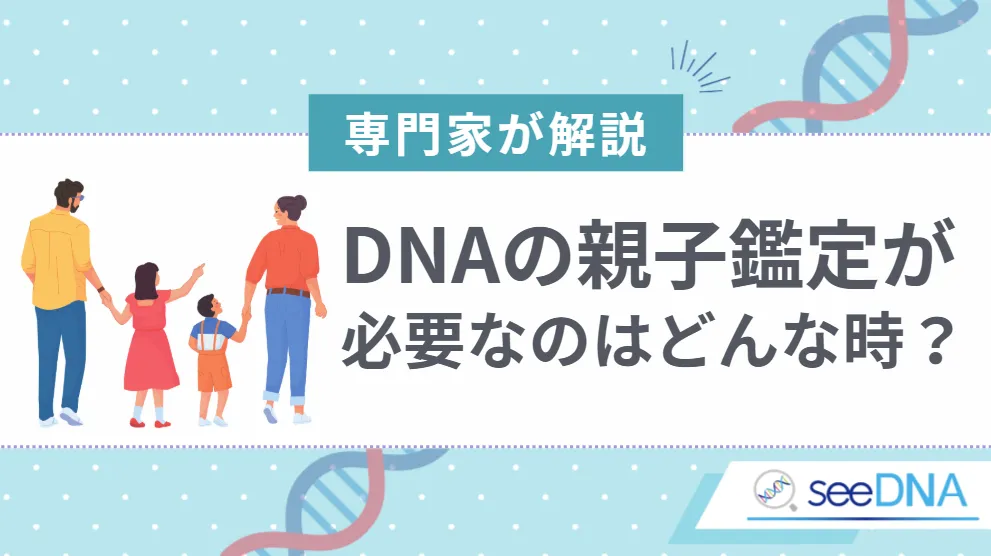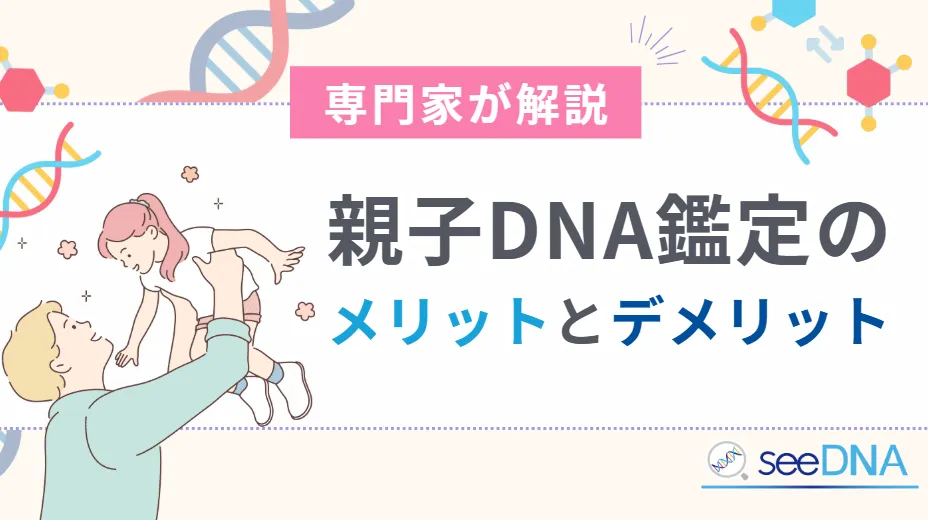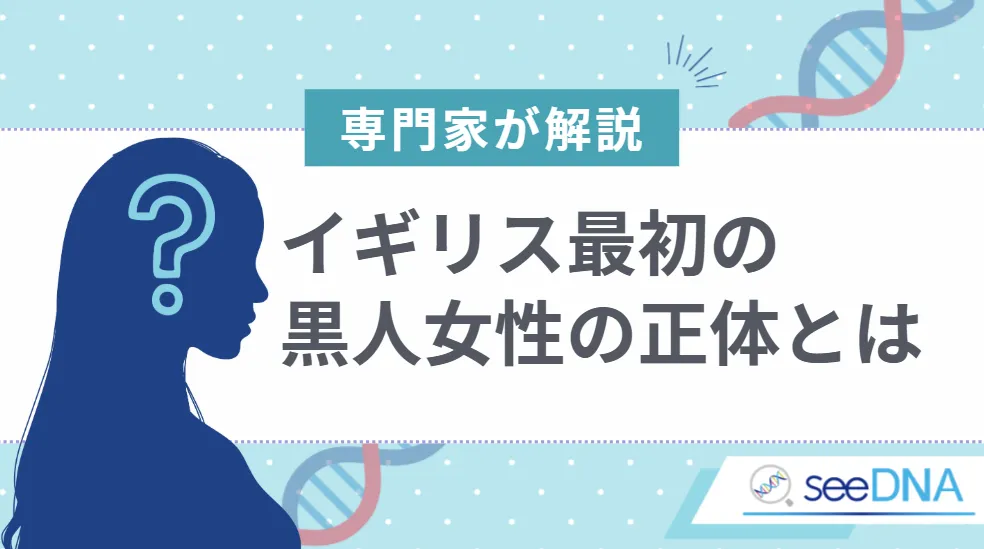【医師が解説】NIPTでわかることは何ですか?
2025.11.24
妊娠がわかった瞬間から、「赤ちゃんは元気に育っているだろうか」「遺伝の病気は大丈夫だろうか」といった不安は、多くの妊婦さんが自然に抱くものです。出生前検査の選択肢が広がった現在、そのなかでも注目を集めているのが NIPT(新型出生前検査)です。NIPTは、母体からの採血だけで赤ちゃんの染色体の状態を高精度で調べられる検査です。
NIPTは従来の羊水検査や絨毛検査と異なり、針を子宮内に刺す必要がないため、流産などのリスクがほとんどありません。妊娠10週前後から検査可能で、結果も約1〜2週間で得られます。
しかし、NIPTは万能な検査ではありません。何がわかり、何がわからないのかを正確に理解することが、検査を受けるかどうかの判断や、結果の解釈において非常に重要です。本記事では、医師の視点からNIPTで検査できる内容とその限界についてわかりやすく解説します。
NIPTで検査できる主な染色体異常

NIPTでは、母体血中の胎児由来DNA(cell-free fetal DNA: cffDNA)を解析することで、特定の染色体異常を高い精度で検出できます。検査対象は大きく分けて、常染色体異常、性染色体異常、微細欠失症候群の3つのカテゴリーに分類されます。
常染色体異常
NIPTの基本検査では、21トリソミー(ダウン症候群)、18トリソミー(エドワーズ症候群)、13トリソミー(パトウ症候群)という3つの常染色体トリソミーを検出します。
21トリソミーに対するNIPTの感度(陽性を正しく検出する確率)は99%以上、特異度(陰性を正しく判定する確率)も99%以上と報告されており(1)、非常に高い精度を誇ります。18トリソミーと13トリソミーについても、感度は95%以上、特異度も99%以上と高い精度を示しています(1)。
これらの染色体異常は、それぞれ特徴的な身体的・発達的な特徴を伴います。21トリソミーは最も頻度が高く、出生700〜1,000人あたり約1人の割合で発生します。18トリソミーや13トリソミーはより重篤で、多くの場合、生後早期に生命に関わる合併症を伴います。
性染色体異常
NIPTでは性染色体(X染色体、Y染色体)の数的異常も検出可能です。主な対象疾患には、ターナー症候群(45,X)、クラインフェルター症候群(47,XXY)、トリプルX症候群(47,XXX)、XYY症候群(47,XYY)などがあります。
性染色体異常の検出精度は常染色体トリソミーと比較するとやや低く、感度は90〜95%程度とされています(2)。これは胎盤モザイク(胎盤と胎児で染色体構成が異なる状態)の影響を受けやすいためです。
性染色体異常は常染色体異常と比べて症状が軽度なことが多く、通常の発達を示す例も少なくありません。しかし、不妊症や学習面での困難さなどを伴う場合があり、早期に診断されることで適切なサポートにつながる可能性があります。
\ダウン症などの遺伝性疾患のリスクがわかる/
微細欠失症候群
施設によっては、染色体の一部が欠失することで生じる微細欠失症候群の検査も提供されています。代表的なものとして、22q11.2欠失症候群(DiGeorge症候群)、1p36欠失症候群、5p欠失症候群(猫鳴き症候群)、Prader-Willi症候群、Angelman症候群などがあります。
ただし、微細欠失症候群のNIPT検査は、常染色体トリソミーの検査と比較して精度が低いことが知られています。感度は概ね60〜90%程度で(ただし報告によって20〜100%とばらつきがある)、偽陽性率(実際には異常がないのに陽性と判定される割合)も高くなります(3)。これは、検出対象となる染色体領域が小さいため、解析の難易度が高いことが理由です。
微細欠失症候群の多くは散発的に発生し、親からの遺伝ではない場合がほとんどです。症状は疾患ごとに異なりますが、知的発達症、先天性心疾患、特徴的な顔貌などを伴うことがあります。
\微小欠失症候群のリスクもわかる/
NIPTでわからないこと・限界

NIPTは優れた検査ですが、いくつかの重要な限界があることを理解しておく必要があります。
確定診断ではない
NIPTはあくまで「スクリーニング検査」であり、「確定診断」ではありません。陽性結果が出た場合でも、必ずしも胎児に染色体異常があるとは限りません。これは、検査が胎児のDNAだけでなく、胎盤由来のDNAも含めて解析しているためです。
胎盤と胎児の染色体構成が異なる「胎盤モザイク」の場合、NIPTの結果と実際の胎児の状態が一致しないことがあります。そのため、NIPTで陽性となった場合は、羊水検査や絨毛検査などの確定検査を受けることが推奨されます。
すべての染色体異常を検出できるわけではない
NIPTは特定の染色体異常を対象とした検査であり、すべての染色体異常や遺伝子疾患を網羅的に調べられるわけではありません。たとえば、染色体の構造異常(転座、逆位など)や、単一遺伝子疾患(血友病、嚢胞性線維症など)は基本的に検出できません。
また、胎児の形態異常(心臓奇形、神経管閉鎖不全症など)もNIPTでは判定できません。これらは超音波検査などの画像診断が必要です。
検査精度に影響する要因
NIPTの検査精度は、母体の体重、妊娠週数、胎盤の状態などさまざまな要因に影響されます。母体の肥満度が高い場合や、双胎妊娠の場合には、胎児由来のDNA濃度が低下し、検査精度が下がることがあります。
また、まれに検査が判定保留となり、再採血が必要になることもあります。これは胎児由来のDNA濃度が十分でない場合などに生じます。
まとめ
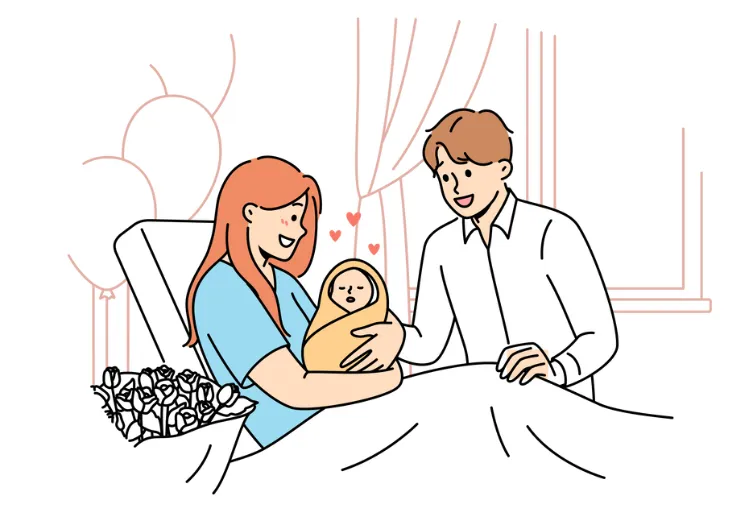
NIPTは母体血液から胎児の染色体異常を高精度で検出できる画期的な検査です。21トリソミー、18トリソミー、13トリソミーといった主要な常染色体トリソミーに対しては非常に高い検出率を示し、流産のリスクなく早期から検査できるという大きな利点があります。
一方で、NIPTはスクリーニング検査であり確定診断ではないこと、すべての染色体異常や先天性疾患を検出できるわけではないことを理解しておく必要があります。陽性結果が出た場合には、確定検査を受けて正確な診断を確認することが重要です。
NIPTを受けるかどうか、どの検査項目を選択するかは、医師とよく相談しながら決めることが大切です。検査の意義と限界を十分に理解したうえで、ご自身とご家族にとって最適な選択をしていただければと思います。
\お腹の赤ちゃんの遺伝性疾患リスクがわかる/
【参考文献】
1.BMJ Open, 2016 Jan.2.Current Genomics, 2022 Nov.
3.Journal of Clinical Medicine, 2022 Jun.
seeDNA遺伝医療研究所の安心サポート
seeDNA遺伝医療研究所は、国際品質規格ISO9001とプライバシー保護のPマークを取得している安心と信頼のDNA鑑定・遺伝子検査の専門機関です。
お腹の赤ちゃん疾患リスクの不安や血縁関係、パートナーの浮気などにお悩みでしたら、DNA鑑定の専門家が、しっかりとご安心いただけるようサポートいたしますのでお気軽にお問合せください。
【専門スタッフによる無料相談】
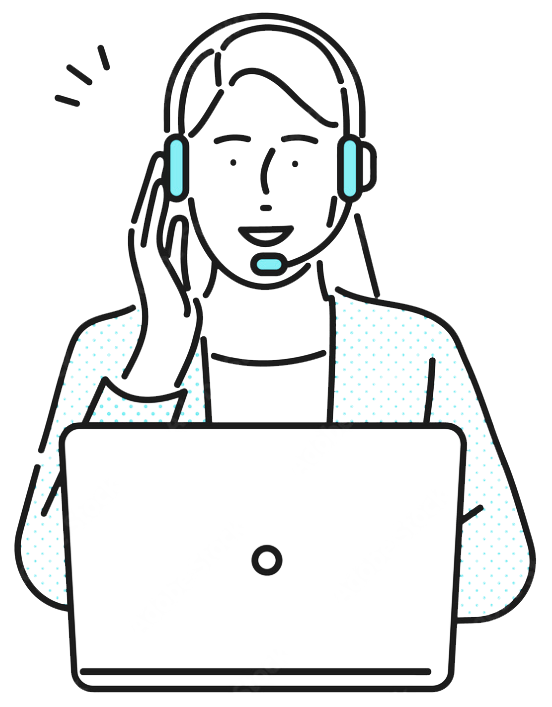
著者
医学博士・医師
広重 佑(ひろしげ たすく)
医学博士、日本泌尿器科学会専門医・指導医、がん治療学会認定医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定産業医、日本抗菌化学療法学会認定医、性感染症学会認定医、Certificate of da Vinci system
Training As a Console Surgeonほか
2010年に鹿児島大学医学部を卒業後、泌尿器科医として豊富な臨床経験を持つ。また、臨床業務以外にも学会発表や論文作成、研究費取得など学術活動にも精力的に取り組んでいる。泌尿器科専門医・指導医をはじめ、がん治療、抗加齢医学、感染症治療など幅広い分野で専門資格を取得。これまで培った豊富な医学知識と技術を活かして、患者様一人ひとりに寄り添った医療を提供している。