【医師が解説】プラダー・ウィリ症候群とは
はじめに
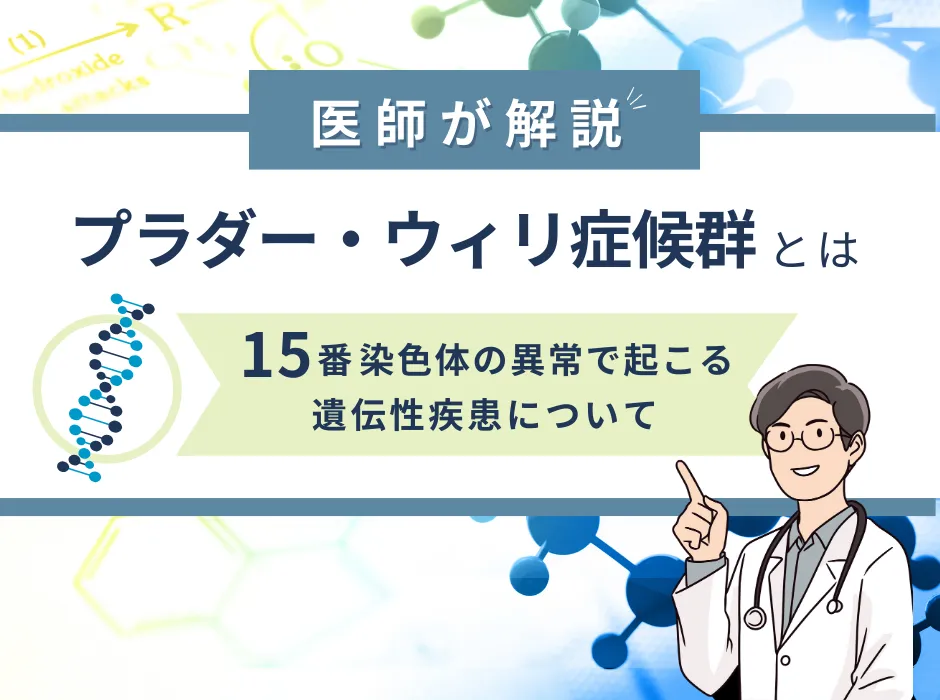
出生前検査をご検討中の妊婦の皆さまへ。
お腹の赤ちゃんの健康について関心をお持ちのことと思います。
今回は、妊娠中に知っておいていただきたい遺伝的疾患の一つ、
プラダー・ウィリ症候群(Prader-Willi Syndrome: 以下PWS)について、分かりやすく解説いたします。
基本知識
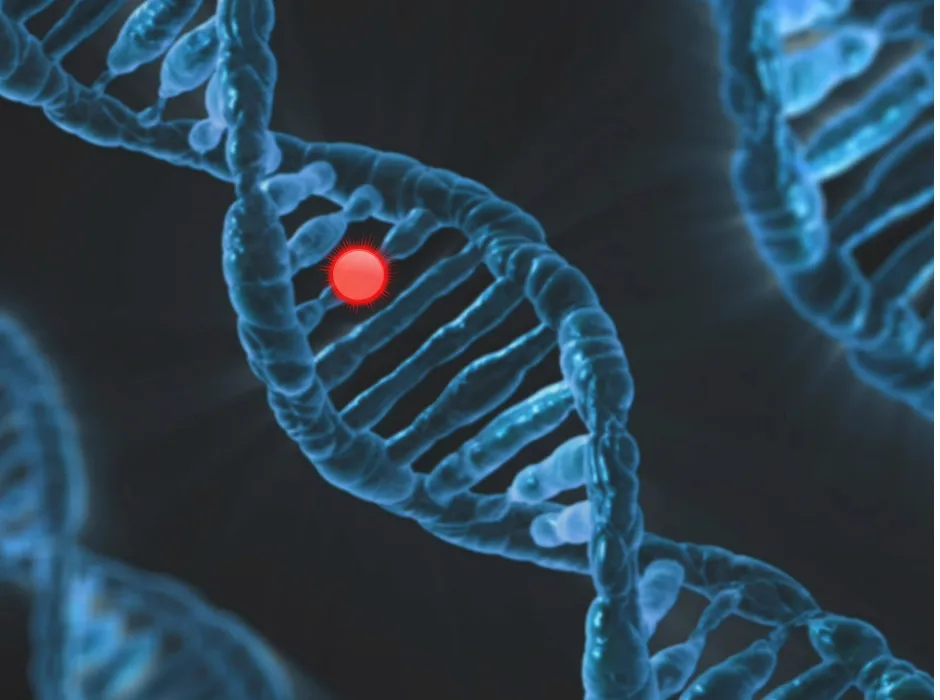
PWSは、1956年に肥満、糖尿病、低身長、性腺機能不全などの内分泌学的異常、
および、発達遅滞、筋緊張低下、特異な性格障害や行動異常などの神経学的異常を呈する症候群として初めて報告された先天性遺伝子疾患で、
現在では約15,000人に1人の頻度で発症することが知られています。※1
発症メカニズムとしては、下記の通りです。※1
- ■ 15番染色体長腕である15q11-q13領域の微細欠失による「欠失型」(約70%)
- ■ 第15染色体が母親からのみ受け継がれる「母性片親性ダイソミー」(約25%)
- ■ メチル化異常による「エピ変異」(約2-5%)
- ■ その他の稀な変異(残り1%未満)
近年の研究により、15番染色体のインプリンティング領域(父親由来の遺伝子だけが働く)にある
「SNORD116」という遺伝子の働きが失われることが、
PWSの発症において極めて重要な要因である可能性が高いと考えられています。※4
大多数の症例に遺伝性はなく、受精後に偶発的に起こるものと考えられています。※1
症状と特徴

◇ 年齢による症状の変化
PWSの症状の特徴は年齢とともに変化し、かつ個人差も大きいことです。※4
- 【新生児期(0-2歳)】筋緊張低下による哺乳障害がほとんどの症例で認められ、 経管栄養が必要になることも多くあります。※5 また、色素低下により頭髪が金髪様(金髪に近い色合い)になることがあり、 男児では停留精巣や男性器の発育不全が90%以上に認められます。※3
- 【幼児期(2-6歳】哺乳障害は改善しますが、全般的な発達遅滞が見られ、 運動発達では、おすわりが12ヵ月、歩行開始が24ヵ月と遅れが生じます。※2
- 【学童期(6-12歳】3〜4歳頃から食への関心が強まり、 平均8歳頃に満腹感のない過食へと移行することが多いと報告されています(小児慢性特定疾病情報センター)。 また、平均IQ60-70の軽度知的障害や特徴的な行動症状が出現してきます。※1,2 さらに、PWS罹患児は複数の重度の学習障害を有し、知能指数(IQ)に比べて学業成績は芳しくない傾向があります。※2
- 【思春期以降(13歳~成人】性腺機能低下により二次性徴の発現が遅れたり欠如したりし、 加えて、易怒性や強迫症状、頑固さといった行動障害が年齢とともに顕著になります。※2 また、PWS罹患成人の25%近く(特に顕著な肥満を有する場合)が2型糖尿病を有し、平均発症年齢は20歳と報告されています。※2
◇ 身体的特徴
顔面の特徴としては、前頭部幅径の狭小化、アーモンド形の眼瞼裂、狭い鼻梁、薄い上赤唇などが見られます。
これらの特徴は出生時に明らかにみられる場合もあれば、そうでない場合もありますが、
一般的に時間の経過とともに徐々に顕著になっていきます。※2
その他にも脊柱側彎症(40-80%)、斜視(40-60%)などの身体的特徴を呈することがあります。※2
予後と生活の質

適切な管理によりPWS患者の予後は改善し、コホート研究では年間死亡率がおよそ1〜1.3%と報告されています。※6
小児期の主な死因は呼吸不全や感染症に伴う突然死であり、
成人期では心疾患・心不全、肺血栓塞栓症、肥満関連合併症、胃の問題(胃破裂、胃壊死)などが報告されています。※2
多くの患者は軽度の知的障害を示しますが、約40%は境界域から正常低値の知能を示します。※2
学童期以降は福祉就労が目標になりますが、知的能力に比べると、職場での適応に問題が多いと言われています。※1
性格は、年齢を経るに従い、可愛いから、しつこい、頑固、パニック、暴力へとエスカレートすることがあり、
行動異常では、万引き、嘘を言うなどの反社会的行動が目立ち、社会の中で適応が困難となることがあります。※3
治療とケア

- ・ 食事療法:
最も重要な基本治療として位置づけられています。
身長1cmあたり10kcalを目安とした摂取カロリー制限とバランスの取れた栄養管理が必要です。※3,4 - ・ 運動療法: 体重維持に重要な役割を果たし、特に水泳などが推奨され、筋力向上と体組成改善に効果があります。※3
- ・ 成長ホルモン補充療法: 身長改善と体組成改善に非常に有効で、筋肉量増加や体脂肪減少効果があり、乳幼児期からの早期開始が推奨されています。※4
- ・ 性ホルモン補充療法: 性機能不全に対する治療として行われ、骨密度改善効果や精神的効果も期待されます。※3
- ・ 向精神薬: 行動・精神症状への対応としては、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)の使用、行動療法などが行われます。※2,3
- ・ インスリン治療: 2型糖尿病の治療では、まず食事・運動療法が基本であり、 必要に応じてメトホルミンやGLP-1受容体作動薬、SGLT2阻害薬などを用います。 症例によってはインスリンを含む薬物療法が検討されます。4
まとめ
PWSは、15番染色体の異常によって起こる遺伝性疾患です。
新生児期には筋肉の緊張が弱く、
力の入りにくさが目立ちますが、成長するにつれて過食や肥満、特有の行動面の特徴が現れるようになります。
このように、症状が年齢に応じて変化していくことが大きな特徴です。
現在は、早期に発見して適切に管理することで、患者さんの生活の質は大きく改善されるようになりました。
治療や支援の中心には、食事療法・運動療法・ホルモン治療などの医療的対応があり、
さらに重要なのはご家族を含めた継続的な支援体制です。
こうした医療の進歩と包括的なサポートの整備により、現在では多くの患者さんが安定した生活を送ることが可能になっています。
\プラダー・ウィリ症候群のリスクがわかる/
seeDNAの安心サポート
seeDNAは、国際品質規格ISO9001とプライバシー保護のPマークを取得している安心と信頼のDNA鑑定・遺伝子検査の専門機関です。
お腹の赤ちゃんの疾患リスクや親子の血縁関係、パートナーの浮気などにお悩みでしたら、遺伝子検査の専門家が、しっかりとご安心いただけるようサポートいたしますのでお気軽にお問合せください。
【専門スタッフによる無料相談】
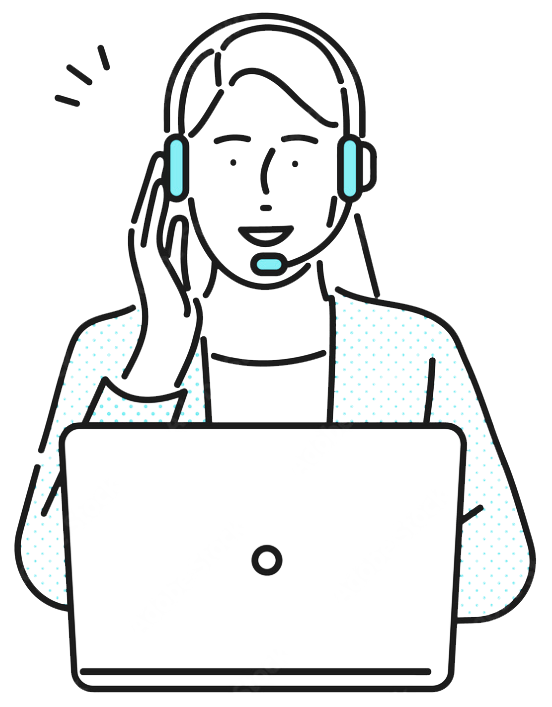
【参考文献】
※1:難病情報センター「プラダー・ウィリ症候群(指定難病193)」 ※2:GRJ プラダー・ウィリ症候群 ※3:小児慢性特定疾病情報センター「プラダー・ウィリ(Prader-Willi)症候群」 ※4:日本小児内分泌学会「プラダーウイリ症候群コンセンサスガイドライン」 ※5:J Clin Res Pediatr Endocrinol, Sep. 2018. ※6:Orphanet J Rare Dis., Nov. 2019.
著者
医学博士・医師
広重 佑(ひろしげ たすく)
医学博士、日本泌尿器科学会専門医・指導医、がん治療学会認定医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定産業医、日本抗菌化学療法学会認定医、性感染症学会認定医、Certificate of da Vinci
system
Training As a Console Surgeonほか
2010年に鹿児島大学医学部を卒業後、泌尿器科医として豊富な臨床経験を持つ。また、臨床業務以外にも学会発表や論文作成、研究費取得など学術活動にも精力的に取り組んでいる。泌尿器科専門医・指導医をはじめ、がん治療、抗加齢医学、感染症治療など幅広い分野で専門資格を取得。これまで培った豊富な医学知識と技術を活かして、患者様一人ひとりに寄り添った医療を提供している。
