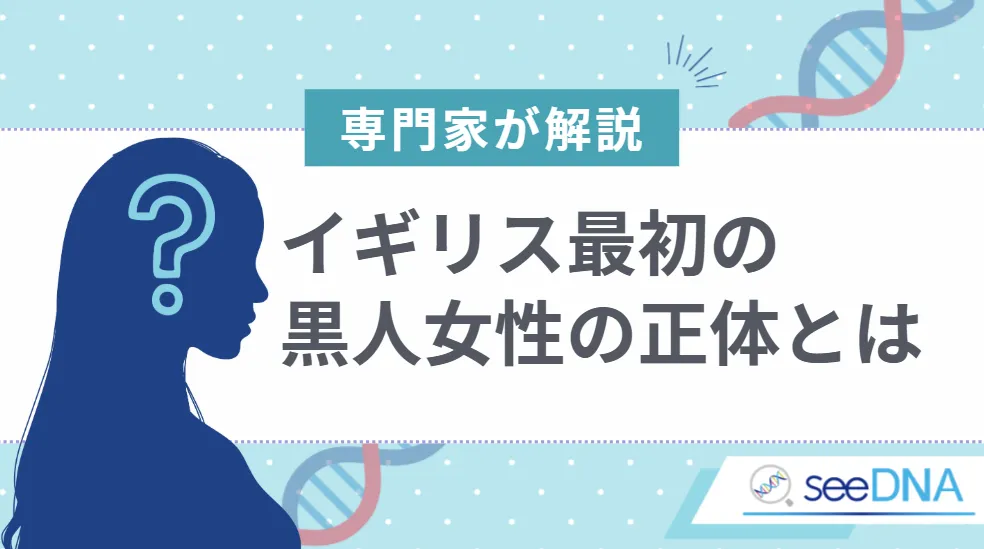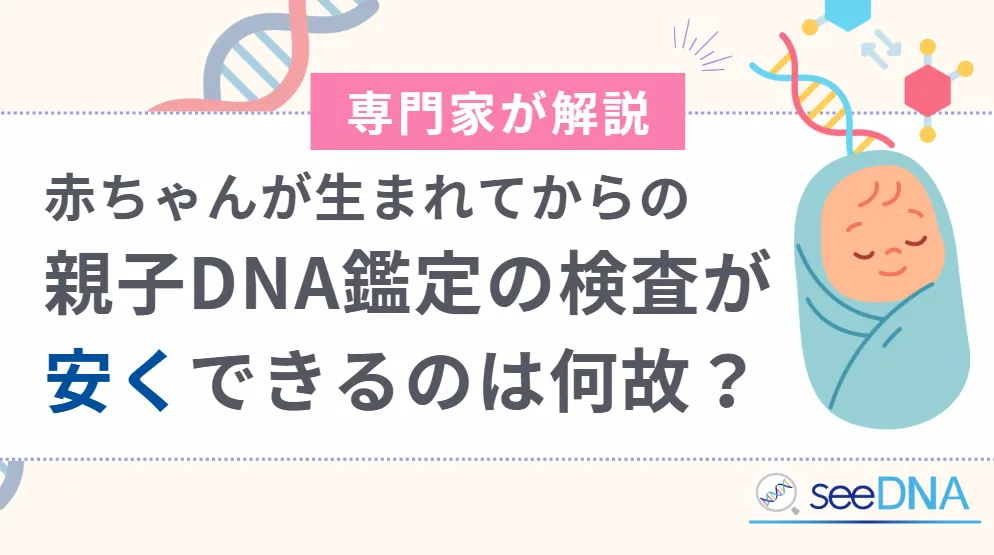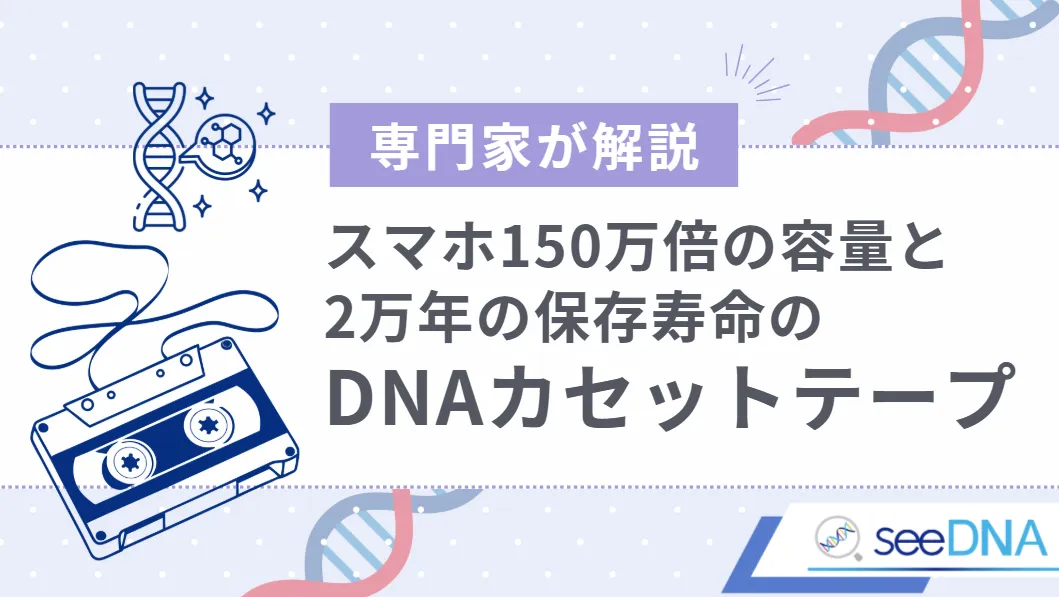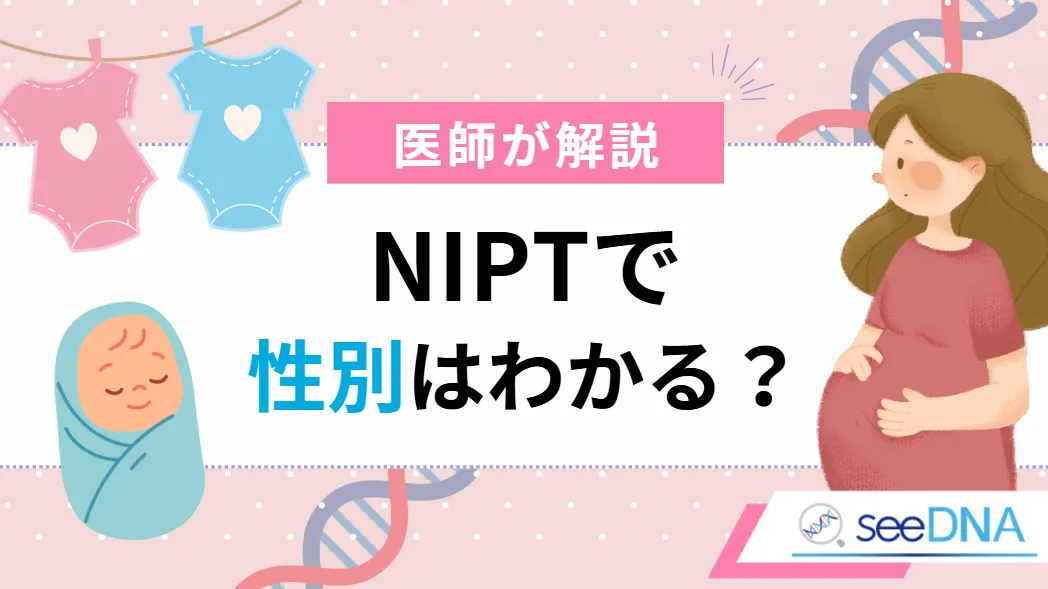NIPT(新型出生前診断)とはどのような検査なの?
2025.09.27
NIPT(新型出生前診断)の基本:検査の仕組みと対象
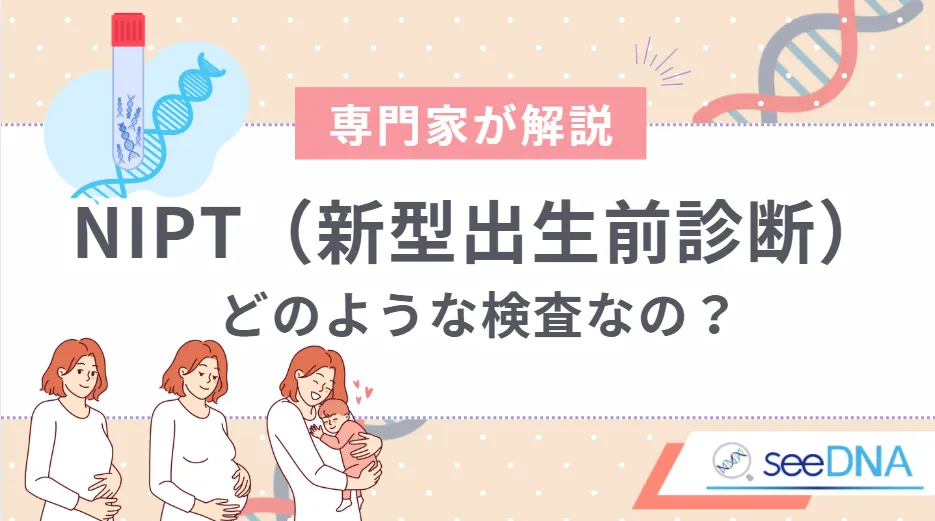
1.NIPTとは何か?:非侵襲性スクリーニング検査の定義
NIPT(Non-invasive prenatal genetic testing)は、日本語では「無侵襲的出生前遺伝学的検査」とも呼ばれ、妊婦さんの血液から胎児の染色体異常のリスクを調べる検査です。
この検査の最大の特徴は、「非侵襲性」であるという点にあります。これは、お腹に針を刺すといった身体的な負担が伴わず、通常の血液検査と同様に、妊婦さんの腕から約10?20 mLの血液を採取するだけで実施できることを意味します。これにより、絨毛検査や羊水検査といった確定診断に比べて、流産や死産のリスクがほぼゼロであることが大きなメリットとして挙げられます。
しかしながら、NIPTはあくまでも「スクリーニング検査」という位置づけです。これは、特定の疾患の可能性が「高いか、低いか」を推定する検査であり、胎児がその疾患を実際に持っているかどうかを「確定診断」するものではありません。このため、NIPTで陽性という結果が出た場合、その診断を確定させるためには、後述する羊水検査や絨毛検査といった確定的検査が必ず必要となります。
2.検査の原理:胎児由来cfDNAの解析
子どもの父親を早期に確定することは、子の福祉に直結する重要な問題です。具体的には、以下のような点が挙げられます。
NIPTの核心的な仕組みは、母体血中に含まれる「cfDNA(cell-free DNA、細胞外DNA)」の解析にあります。
妊娠中、妊婦さんの血液中には、妊婦さん自身の細胞由来のDNA断片と、胎盤の細胞由来のDNA断片が混在しています。胎盤の細胞のDNAは、通常、胎児のDNAとほぼ同一であるため、この胎盤由来cfDNAを解析することで、胎児の遺伝情報の一部を推定することが可能になるのです。
具体的には、採取した血液からcfDNAを抽出し、「次世代シークエンサー(NGS)」という高度な機器を用いて、DNA断片の数を網羅的に測定・解析します。特定の染色体に由来するDNA断片の数が通常よりも多いか少ないかを調べることで、染色体数の異常(異数性)の可能性を判定します。例えば、ダウン症候群は21番染色体が通常より1本多い3本ある状態ですが、NIPTでは21番染色体に由来するcfDNAの量が他の染色体よりも多いことを検出することで、その可能性を推定します。
検査の精度には、母体血中に占める胎盤由来cfDNAの割合(「胎児DNAの割合」または「fetal fraction」)が重要となります。この割合が低い場合、正確な判定が難しくなるため、一般的に妊娠10週以降に検査が推奨されています。
3.NIPTでわかること:スクリーニングの対象疾患
日本国内において、日本医学会が運用する出生前検査認証制度に準拠する施設(以下、認証施設)では、NIPTの検査対象を主に以下の3つの常染色体トリソミーに限定しています 12。
- 21トリソミー(ダウン症候群): 21番染色体が3本ある状態です。
- 18トリソミー(エドワーズ症候群): : 18番染色体が3本ある状態です。
- 13トリソミー(パトウ症候群): 13番染色体が3本ある状態です。
これらの疾患は、妊婦さんの年齢が高いほど発症率が高くなることが知られています。
しかし、日本のNIPT市場には、公的な指針に準拠しない一部の民間検査機関も存在し、広範な検査サービスを提供している実態があります。
例えば、seeDNA遺伝医療研究所は、上記の3つのトリソミーに加え、ターナー症候群やクラインフェルター症候群といった性染色体異数性や、1番から22番の全染色体異数性、さらに微細欠失症候群までを検査対象に含めていることを公表しています。この状況は、公的指針が慎重な倫理的観点から検査範囲を限定している一方で、技術の発展と多様な妊婦さんのニーズが、指針の枠外で広範な検査サービスを生み出していることを示唆しています。
これらの検査結果が持つ意味をより深く理解していただくため、対象となる疾患の医学的・社会的な背景情報を以下にまとめます。
| 疾患名 | 罹患率(日本) | 主な症状・予後 |
|---|---|---|
| 21トリソミー(ダウン症候群) | 出産時の年齢が20歳で2,000人に1人、40歳で100人に1人 |
知的障害や先天性心疾患(約50%に合併)を伴います17。 近年では医療の進歩により平均寿命が約60歳前後まで延びていますが、呼吸器感染症や生活習慣病への注意が必要です20。 |
| 18トリソミー(エドワーズ症候群) | 3,500?8,500人に1人 |
重度の先天性心疾患を約50%が合併します。 妊娠10週以降におよそ85%の赤ちゃんが胎内で亡くなるという報告もあります。 生まれた場合でも予後は非常に厳しく、半数以上が生後1週間以内に、90?95%が1歳までに亡くなります。 ただし、近年では積極的な医療介入により予後が改善するケースも報告されています。 |
| 13トリソミー(パトウ症候群) | 不明(21トリソミー、18トリソミーに次いで多い) |
重度の心疾患や脳の奇形、口唇口蓋裂などを伴います。 予後が非常に厳しく、約80%が生後1か月以内に亡くなり、1年以上生存できる割合は10%未満です。 しかし、近年では積極的な治療によって10年以上生存する例も増えてきています。 |
NIPTの精度と限界:正しい理解のために

1.スクリーニング検査としての位置付け:確定診断ではない理由
NIPTは非常に高精度な検査ですが、100%ではありません。したがって、検査結果が「陽性」であったとしても、それはあくまで「胎児が対象疾患を有している可能性が高い」ことを示すものであり、絶対的な診断ではありません。このため、陽性という結果が出た場合、確定的な診断のためには、絨毛検査や羊水検査といった侵襲的な検査を受けることが推奨されています。
2.検査精度の評価指標:感度、特異度、陽性的中率(PPV)
NIPTの精度を理解するためには、いくつかの重要な指標を知る必要があります。
- 感度(Sensitivity): 胎児が実際に染色体異常を持つ場合に、検査結果が陽性となる確率を指します。21トリソミー(ダウン症候群)の場合、NIPTの感度は99%と非常に高いことが知られています。
- 特異度(Specificity):胎児が染色体異常を持たない場合に、検査結果が陰性となる確率を指します。21トリソミーの場合、NIPTの特異度も99%です。
- 陽性的中率(PPV, Positive Predictive Value):検査結果が陽性だった場合に、実際に胎児が対象疾患を持っている確率です 17。この指標は、妊婦さんの年齢や疾患の有病率によって大きく変動する点が最も重要です。例えば、21トリソミーの陽性的中率は、30歳の妊婦さんで61.3%、35歳で79.9%、40歳で93.7%と、年齢が上がるにつれて顕著に上昇します。
このデータは、若年層の妊婦さんがNIPTで陽性判定を受けた場合、それが「偽陽性」、つまり実際には胎児に染色体異常がない可能性が比較的高いことを意味しています。この事実は、単に「精度が高い」という情報だけで判断せず、検査結果を安易に受け止めずに、必ず確定診断を行う必要があることの強力な根拠となります。
3.偽陽性・偽陰性の原因
NIPTの結果に偽陽性や偽陰性が生じる主要な原因の一つに、「胎盤性モザイク(Placental Mosaicism)」現象が挙げられます。これは、胎児自身の染色体は正常であるにもかかわらず、胎盤の一部にのみ染色体異常が存在する状態です。NIPTは胎盤由来のcfDNAを解析するため、この胎盤の異常なDNAが検出され、結果として「偽陽性」と判定されることがあります。
逆に、胎盤が正常で、胎児にのみモザイク状態が存在する場合は、検査結果が「陰性」であっても、実際には胎児に異常がある「偽陰性」となる可能性も指摘されています。このような現象が存在するため、NIPTの結果は100%ではないと理解し、結果が陽性であった場合には、確定診断によって必ず確認することが不可欠となります。
他の出生前検査との比較

1.非確定的検査との比較
NIPTは、他の非確定的検査と比べて高い精度を誇ります。
妊娠初期の胎児精密超音波検査は妊娠11?13週頃、母体血清マーカー検査は妊娠15?17週頃に行われるのに対し、NIPTは妊娠10週から検査可能であり、より早い段階で検査結果を得ることができます。
また、感度を比較すると、NIPTの21トリソミーに対する感度が99%であるのに対し、母体血清マーカー検査(クアドラプルテスト)の感度は約81%と、NIPTの方が格段に高いことがわかります。この高い感度により、NIPTで陰性判定が出た場合、胎児に染色体異常がある可能性は非常に低いと判断できます。
2.確定的検査との比較:羊水検査と絨毛検査
NIPTがスクリーニング検査であるのに対し、羊水検査や絨毛検査は、それだけで診断が確定する「確定的検査」です。これらの検査では、胎児の細胞を直接採取して分析するため、染色体異常の有無をほぼ100%の精度で確定診断することができます。
しかし、これらの検査は、子宮内に針を刺すという「侵襲的」な手技であるため、ごくわずかではあるものの、流産・死産のリスクが伴います。絨毛検査の流産リスクは0.2?1%、羊水検査の流産リスクは0.1?0.3%と報告されていますが、近年の超音波技術の進歩や医師の経験により、リスクはさらに低下しているという報告も出ています。
NIPTは、この侵襲的な確定診断を必要とするか否かを判断するための「入り口」としての役割を担っています。
| 検査の種類 | 検査方法 | 検査時期 | 診断の確定度 | 流産・死産リスク |
|---|---|---|---|---|
| NIPT(非確定的検査) | 採血 | 妊娠10?16週頃 | 推定(スクリーニング) | ほぼゼロ |
| 絨毛検査(確定的検査) | 胎盤の一部を採取 | 妊娠11?14週頃 | ほぼ100% | 0.2?1% |
| 羊水検査(確定的検査) | 羊水を採取 | 妊娠15?18週頃 | ほぼ100% | 0.1?0.3% |
NIPTと日本の医療・社会における位置付け

1.日本国内の指針と認証制度
NIPTの実施に関して、日本では日本医学会による「出生前検査認証制度」が運用されています。この制度のもと、検査を実施する施設は、十分な遺伝カウンセリング体制を持つ「基幹施設」またはその「連携施設」として認証される必要があります。
認証施設では、不特定多数の妊婦さんを対象としたマススクリーニングを避けるため、NIPTの対象となる妊婦さんを特定の条件に限定しています。具体的には、高年齢の妊婦さん、胎児超音波検査で染色体異常の可能性が示唆された方、母体血清マーカー検査で可能性が示唆された方などが対象とされています。
2.遺伝カウンセリングの重要性
NIPTを受ける前後には、遺伝カウンセリングが必須とされています。これは、NIPTが物理的には採血のみで非侵襲的である一方で、その結果が妊婦さんやご家族に深刻な精神的・心理的影響を及ぼす可能性があるためです。特に偽陽性の場合は、陽性結果がもたらす不安やストレスは大きな負担となり得ます。
遺伝カウンセリングは、この「物理的非侵襲性」と「心理的侵襲性」のギャップを埋めるための不可欠なプロセスです。専門家である医師や認定遺伝カウンセラーは、検査の限界(偽陽性・偽陰性)や結果が持つ意味、そして陽性であった場合の選択肢(確定診断、出産後の医療計画、心理的準備など)について、中立的な立場で情報提供と対話を行います。これにより、妊婦さんが十分な情報に基づき、自らの価値観に沿って主体的な意思決定を行えるようサポートします。
3.NIPTが提起する倫理的・社会的課題
NIPTの普及は、社会全体に様々な倫理的・社会的な課題を提起しています。
- 「命の選別」との懸念: NIPTは、出生前診断が「障害を持つ命の排除」につながるのではないかという倫理的懸念を引き起こしています。日本の母体保護法では、胎児の疾患や障害を理由とした人工妊娠中絶は認められていません。にもかかわらず、NIPTの陽性結果が出た場合に妊娠中断を選択する割合が高いという指摘があり、これは妊婦さんが十分に情報を得られずに決断を迫られている可能性を示唆しています。
- 滑りやすい坂の懸念(Slippery Slope): 遺伝学の技術が社会の倫理観をはるかに超えるスピードで進歩していることへの懸念も指摘されています。検査対象が拡大し、より多くの遺伝情報が判明するにつれて、「どのような遺伝情報であれば検査をすべきか」「その情報をどう扱うべきか」という新たな倫理的課題が常に生じています。
- 情報格差とアクセス:公的指針に準拠しない施設が提供する広範な検査サービスは、必ずしも十分な遺伝カウンセリングを伴わない可能性があります。また、保険適用外の検査費用は、NIPTへのアクセスに経済的な格差を生じさせています。
結論と受検を検討されている方へのメッセージ

NIPTは、採血のみで早期に、しかも高い精度で主要な染色体異常のリスクを推定できる、画期的な検査です。しかし、この検査の真価を理解するためには、その技術的な側面だけでなく、スクリーニング検査としての限界、偽陽性や偽陰性の可能性、そして結果がもたらす心理的・倫理的な側面を十分に認識しておくことが不可欠です。
NIPTは、決して「受けるべき」あるいは「受けないべき」と一概に決められる検査ではありません。この検査は、ご本人とご家族が、検査の原理や限界、日本の医療体制、そして社会的背景について専門家から十分な情報とサポートを得た上で、自らの価値観に基づいて主体的に選択すべきものです。
万が一、検査で陽性という結果が出た場合でも、一人で悩みを抱え込む必要はありません。認証施設では、陽性結果後の遺伝カウンセリングが原則として義務付けられており、必要に応じて小児科専門医との面接も可能となっています。また、seeDNA遺伝医療研究所のように確定診断の費用を一部補助する制度を設けている施設もあります。
NIPTは、これからの妊娠・出産を考える上で一つの選択肢となり得ます。検査を検討される際には、まずは信頼できる医療機関で専門家と十分に相談されることを心からお勧めいたします。
\お腹の赤ちゃんの遺伝性疾患リスクがわかる/
seeDNA遺伝医療研究所の安心サポート
seeDNA遺伝医療研究所は、国際品質規格ISO9001とプライバシー保護のPマークを取得している安心と信頼のDNA鑑定・遺伝子検査の専門機関です。
お腹の赤ちゃんの親子の血縁関係や疾患リスク、パートナーの浮気などにお悩みでしたら、遺伝子検査の専門家が、しっかりとご安心いただけるようサポートいたしますのでお気軽にお問合せください。
【専門スタッフによる無料相談】
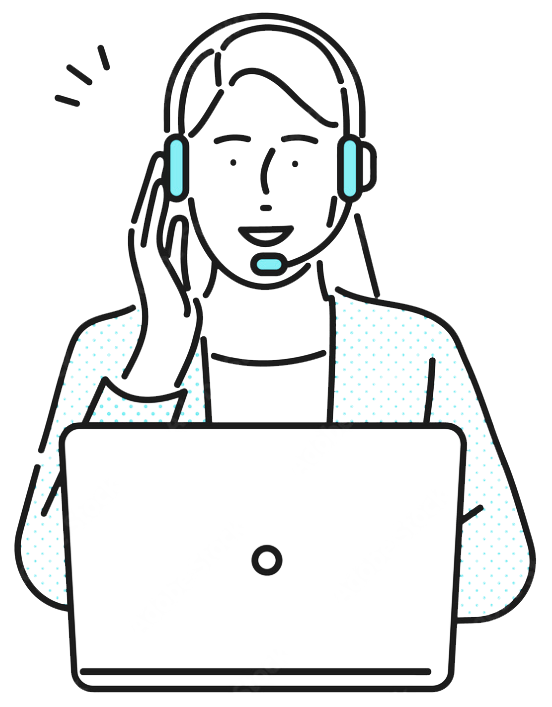
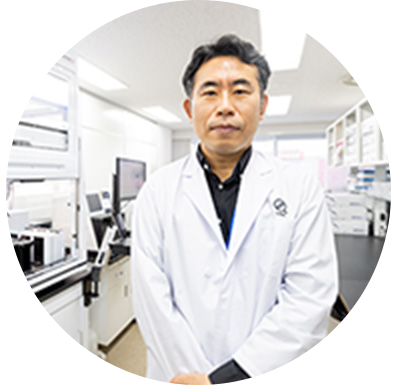 著者
著者
医学博士 富金 起範
筑波大学、生体統御・分子情報医学修士/博士課程卒業
2017年に国内初となる微量DNA解析技術(特許7121440)を用いた出生前DNA鑑定(特許7331325)を開発